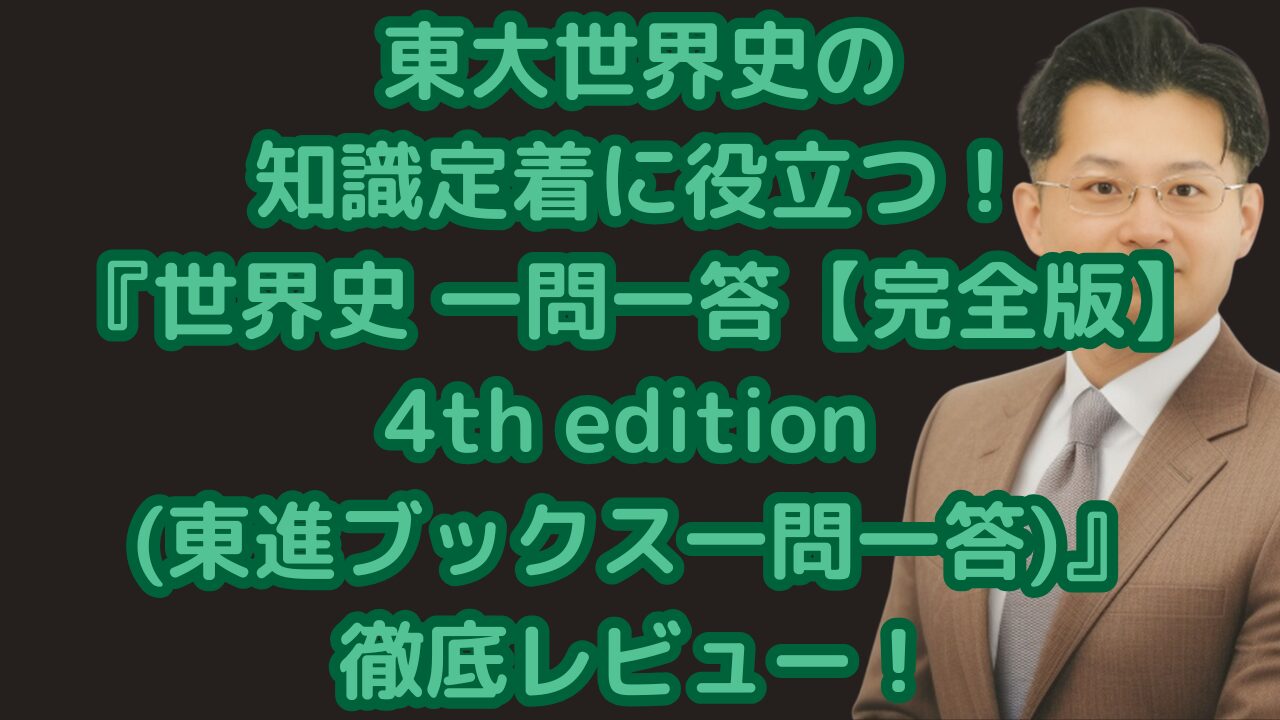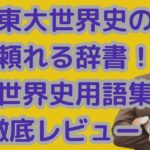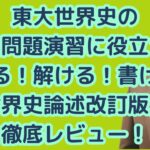東大世界史の得点を大きく左右するのは、「知識の正確さと定着度」です。
論述問題が重視される東大世界史ですが、基礎知識があやふやなままでは論述問題で点をとることはできません。
そんな世界史の土台固めに最適なのが、『世界史 一問一答【完全版】4th edition』です。
2024年の新課程に対応し、最新の学習指導要領に基づいた全3,500問以上の問題が収録されています。
「世界史を効率よく暗記したい」「論述に必要な知識を確実に定着させたい」と考えている東大志望者の皆さんにとって、この一冊がどのように役立つのかを詳しくレビューしていきます!
- 1:『世界史 一問一答【完全版】4th edition (東進ブックス一問一答)』とは
- 2:『世界史 一問一答【完全版】4th edition (東進ブックス 一問一答)』の使用タイミングと使用目的
- 3:『世界史 一問一答【完全版】4th edition (東進ブックス 一問一答)』の特徴とメリット
- 4:『世界史 一問一答【完全版】4th edition (東進ブックス 一問一答)』の効果的な使い方
- 5:『世界史 一問一答【完全版】4th edition (東進ブックス 一問一答)』の使用上のNG行為
- 6:『世界史 一問一答【完全版】4th edition (東進ブックス 一問一答)』を実際に使った受験生の声
- 7:この記事(『世界史 一問一答【完全版】4th edition (東進ブックス 一問一答)』の記事)のまとめ
- 8:最後に
1:『世界史 一問一答【完全版】4th edition (東進ブックス一問一答)』とは
基本情報
| 項目 | 内容 |
| 監修 | 加藤和樹 |
| 出版社 | ナガセ |
| 発売日 | 2024年7月26日 |
| 定価 | 1,320円 |
| ページ数 | 520ページ |
基本構成
本書は、一問一答形式の用語問題集です。
各問題の頻出度が「☆の数」で示されており、学習の優先順位をつけやすくなっています。
- ☆☆☆(最頻出):1,933問
- ☆☆(頻出):1,304問
- ☆(難関):355問
- 星なし(超ハイレベル):最難関レベル
また、以下のアイコンが付記されており、学習時の補助となります。
- ◆ … 関連知識や補足事項
- 👉️ … 学習時のアドバイス
- ⚠ … 受験生がよく間違えるポイント
さらに、☆☆☆レベルの問題には朗読音声が付属しており、耳からも知識をインプットすることができます。
目次の概要
本書は、時代ごとに体系的に学習できるように構成されています。
第1部:前近代
Ⅰ. 古代オリエントと地中海世界
Ⅱ. イラン・南アジア・東南アジア世界の成立
Ⅲ. 前近代の東アジア世界
Ⅳ. イスラーム世界の成立と発展
Ⅴ. ヨーロッパ世界の成立と発展
Ⅵ. アジア諸地域の発展
第2部:近代
Ⅶ. 近代ヨーロッパの成立
Ⅷ. 近代ヨーロッパ世界の拡大と展開
Ⅸ. 近代国民国家の発展
Ⅹ. 帝国主義とアジア諸地域の民族運動
Ⅺ. 2つの世界大戦
第3部:現代
Ⅻ. 冷戦の時代
ⅩⅢ. 現代の世界
このように、本書は世界史を前近代・近代・現代の三部構成で体系的に整理しながら、通史の流れを意識して学習できるようになっています。
2:『世界史 一問一答【完全版】4th edition (東進ブックス 一問一答)』の使用タイミングと使用目的
使用タイミング
本書は、世界史の知識を効率的に定着させるために以下のタイミングで活用するのがおすすめです。
① 通史のインプットと並行して使用する
『実況中継』や『ナビゲーター』などのインプット教材を読んだ後にその範囲の一問一答を解くことで、知識の定着を図ることができます。
ただ読むだけでは忘れやすいですが、すぐにアウトプットすることで記憶に残りやすくなります。
② 論述演習と並行して使用する
東大世界史では論述が重要ですが、第3問のような知識問題も確実に得点する必要があります。
論述対策と並行して一問一答を解くことで基礎知識を補強し、より正確な記述ができるようになります。
③ 併願私立の対策として使用する
早慶などの私立大学では知識問題が多く出題されるため、一問一答形式の学習が非常に有効です。
私立対策を入念に行うことで、東大二次試験当日に「〇〇大学◯学部には合格した」という精神的に安定した状態で試験に臨むことができます。
使用目的
本書を活用することで、以下のような力を身につけることができます。
✅ 世界史の用語を効率よく覚える
用語の頻出度(☆の数)を参考にしながら、優先順位をつけて学習できます。
✅ 論述問題を解く際の基礎・土台となる知識を身につける
世界史の論述では、流れや因果関係を理解することが重要です。
一問一答を通じて基本的な事実関係を整理することで、論述の精度も向上します。
✅ 東大世界史第3問で全問正解を目指せる知識を習得する
東大世界史の第3問は知識問題のため、本書を繰り返し解くことで確実に得点できる力を養えます。
3:『世界史 一問一答【完全版】4th edition (東進ブックス 一問一答)』の特徴とメリット
『世界史 一問一答【完全版】4th edition』の特徴とメリットについて詳しくご紹介します。
① 最新のカリキュラムに対応
2024年に発売された最新版のため、「世界史探求」や「歴史総合」といった新課程に対応しています。
これにより、最新の入試傾向に沿った学習が可能です。
② 頻出度が☆の数で示され、学習の優先度が明確
本書の最大の特徴のひとつは、用語の頻出度が「☆の数」でランク付けされていることです。
この分類によって優先的に学習すべき問題が一目で分かり、効率的な学習が可能になります。
③ 実際の入試問題の出題形式を活かした問題文
本書の問題文は実際の入試で問われた形をなるべくそのまま活かしているため、演習を通じて実戦力が身につきます。
問題文をそのままの形で覚えておくだけで得点できる記述問題も存在するため、単なる用語暗記に留まらず、入試本番での応用力を高めることができるのが魅力です。
④ 東大世界史の論述対策にも役立つ構成
一問一答形式ですが、問題文の順序や内容が出来事の流れや因果関係を意識して構成されているため単なる知識の羅列ではなく、通史の理解を深めながら暗記ができるようになっています。
これは、論述問題の土台作りにもつながります。
⑤ 赤シート対応で効率的に暗記ができる
☆☆☆~☆☆レベルの重要語は赤文字で書かれており、赤シートを使って隠しながら学習できるようになっています。
スキマ時間の学習にも最適です。
⑥ プロのナレーターによる朗読音声付き
本書の☆☆☆レベルの問題文は歴史・教育系のナレーションに特化したプロのナレーターが朗読しており、音声を繰り返し聴くことで耳からも知識を定着させることができます。
通学時間や寝る前の時間を活用し、視覚と聴覚の両方を使った学習が可能です。
⑦ コンパクトなサイズで持ち運びやすい
本書はコンパクトなサイズで設計されており、持ち運びがしやすいため外出先や移動中の学習にも適しています。
4:『世界史 一問一答【完全版】4th edition (東進ブックス 一問一答)』の効果的な使い方
本書を最大限活用するためには、「どのタイミングで、どのように使うか」が重要です。
ただ漫然と解くだけではなく、効率よく知識を定着させるための具体的な学習法を紹介します。
① 通史のインプット学習と並行して演習を行う
世界史の通史学習(『実況中継』『ナビゲーター』など)を進める際に、読んだ範囲の一問一答を解くことで知識の定着を図ります。
✅ 「読むだけ」ではなく、「解く」ことで記憶に定着しやすくなる!
✅ 授業や参考書で学習した直後に取り組むことで、短期記憶から長期記憶へと変換できる!
学習サイクルの一例として、以下のような流れで進めると効果的です。
・参考書で通史を学習する(例:『ナビゲーター』の中世ヨーロッパを読む)
・該当範囲の一問一答を解く(☆☆☆と☆☆の問題を優先)
・間違えた問題にチェックをつけ、翌日以降に復習する
② チェックボックスを活用し、全問正解するまで繰り返す
本書にはチェックボックスがついているため、間違えた問題を記録してできるようになるまで繰り返すことが大切です。
📌 効果的な活用法
- 1周目:とにかく解いてみる(間違えた問題にはチェック)
- 2周目以降:チェックのついた問題を中心に繰り返す
- 最終段階:チェックがなくなるまで繰り返し、完全習得
特に東大世界史は「正確な知識」が求められるため、知識があやふやな問題を放置せず、確実に覚えることが重要です。
③ ☆レベルの問題も必ず覚える(論述・私立対策に有用)
「☆レベルの問題は難しいから飛ばしていい?」と思うかもしれませんが、☆問題に論述頻出の重要用語が含まれていることがあるため、必ず覚えるようにしましょう。
例えば、
- 「香辛料」(ローマ帝国と南インドの東西交易で取引された物品として)
- 「グーツヘルシャフト」(東欧の農奴制と西欧の資本主義の対比)
は☆レベルとされていますが、論述の中で因果関係を説明する際に不可欠な用語です。
また、早慶などの私立大学では☆レベルの用語が出題されることも多いため、私立対策としても有効です。
④ 朗読音声を活用し、耳からも学習する
本書の☆☆☆レベルの問題には朗読音声が付属しており、聞き流し学習が可能です。
📌 おすすめの活用方法
・通学時間に音声を聞く(スキマ時間を有効活用)
・寝る前に流して記憶を強化する(睡眠中に記憶が整理される)
・暗記の復習時に音声を併用する(目と耳の両方を使うと記憶に残りやすい)
音声を活用することで、視覚だけでなく聴覚も使った学習が可能となり、定着率が向上します。
5:『世界史 一問一答【完全版】4th edition (東進ブックス 一問一答)』の使用上のNG行為
本書は世界史の知識を効率よく定着させるために最適な問題集ですが、誤った使い方をすると効果が半減してしまいます。
ここでは、やってはいけないNG行為について解説します。
① インプット教材とセットで使わない(いきなり一問一答のみで始めてしまう)
一問一答は知識の確認・定着を目的とした教材です。
まだ習っていない範囲を解こうとしても単なる暗記作業になってしまい、背景や流れを理解することができません。
📌 正しい使い方
➡ まずは通史の学習(『ナビゲーター』『実況中継』など)をし、その後に対応する範囲の一問一答を解く。
➡ 知識が整理された状態でアウトプットすることで、定着率が大幅にアップする!
② 反復演習をしない
NG例:「一度解いたからもう大丈夫!」と思い込み、復習しない
人間は一度覚えたことをすぐに忘れてしまいます。
一問一答は「解く → 覚える → 解く→覚える…」のサイクルが非常に重要です。
📌 正しい使い方
➡ 最低3~4周は繰り返す!(間違えた問題にチェックを入れ、重点的に復習)
➡ 1回目:間違えた問題にチェック → 2回目以降:チェックした問題だけ解き直す
➡ 完全に覚えた問題からチェックを外していき、最終的にチェックがゼロになるまで繰り返す!
③ 既に覚えた問題とそうでない問題を区別せず、すべての問題を何度も解く
NG例:すでに覚えている問題も含めて何度も解き続ける
一見すると「復習になるから良さそう」と思うかもしれませんが、これは非効率的です。
すでに覚えている問題に時間を使うよりも、まだ覚えていない問題に集中する方が効果的です。
📌 正しい使い方
➡ チェックボックスを活用し、間違えた問題だけを繰り返し解く!
➡ 暗記が完了した問題はチェックを外し、復習対象から除外する
➡ 最終的には間違えた問題だけを解く形にして、効率的に学習を進める
④ 夏までに全部覚えて、あとは入試まで放置する
NG例:「夏の間に一気に覚えて、あとは論述や過去問に集中しよう!」と考える
世界史の知識は、定期的に復習しなければすぐに忘れてしまうものです。
夏の間に完璧に覚えたつもりでも、秋・冬になって見直してみると、忘れていることがよくあります。
📌 正しい使い方
➡ 夏までに一通り覚えるのは良いが、その後も定期的に復習する!
➡ 秋・冬・直前期には、論述対策や過去問演習と並行して、一問一答を復習する時間を確保する
➡ 「論述対策に集中するから」といって一問一答を放置すると、基礎知識が抜け落ち、論述の質も低下するので注意!
6:『世界史 一問一答【完全版】4th edition (東進ブックス 一問一答)』を実際に使った受験生の声
実際に本書を使った受験生の声を、「良かった点」と「いまいちだった点」に分けて紹介します!
【良かった点】
🗣 「赤シートで隠せるから、スキマ時間にサクッと勉強できる!」
👉 通学中や休み時間に、サッと取り出して勉強できるのがめっちゃ便利。赤シートで消えるから、わざわざノートを開かなくても暗記できるのが助かった!
🗣 「朗読音声があるのがありがたい!耳からも覚えられるから定着しやすい。」
👉 家で机に向かって勉強するだけじゃなくて、移動中とか寝る前に音声を聞きながら勉強できるのが良かった。耳から聞くと、意外と記憶に残りやすい!
🗣 「用語の並び順がちゃんと流れを意識して作られているから、論述にも役立つ!」
👉 ただの暗記本じゃなくて、歴史の流れがちゃんと意識されてる。だから、論述問題のときに「この出来事の前に何があったっけ?」って考えたときに、思い出しやすくなる!
🗣 「頻出度の☆の数がめっちゃ便利。優先順位をつけて勉強しやすい!」
👉 どこまで覚えればいいかがハッキリ分かるのが良かった。とりあえず☆☆☆から攻めて、余裕があれば☆の問題にもチャレンジ、みたいな感じで計画を立てやすかった!
【いまいちだった点】
🗣 「超ハイレベルの問題はさすがに難しすぎて、どこまでやるべきか迷う……。」
👉東大志望とはいえ、星なし(超ハイレベル)の問題はほんとに細かい知識が多くて、全部やるべきか悩んだ。正直、☆☆☆と☆☆の問題を完璧にする方が大事かも?
🗣 「分厚いから持ち運びにちょっと不便。電子版があればもっと便利かも?」
👉 コンパクトとはいえ、やっぱり520ページあるからカバンに入れるとまあまあ重い(笑)。電子版があればスマホでチェックできるのにな~って思った!
7:この記事(『世界史 一問一答【完全版】4th edition (東進ブックス 一問一答)』の記事)のまとめ
📌 『世界史 一問一答【完全版】4th edition』の特徴
✅2024年対応版で「世界史探求」「歴史総合」に準拠
✅全3,500問以上収録され、頻出度が☆の数で示されている
✅歴史の流れを意識した構成で、論述対策にも活用できる
✅赤シート対応&朗読音声付きで、効率的に暗記が可能
✅コンパクトサイズで持ち運びしやすい(ただし分厚め)
📌 効果的な使い方
✅通史のインプットと並行して 一問一答を活用し、知識を定着させる
✅チェックボックスを利用し、間違えた問題を重点的に復習
✅☆レベルの問題も覚えることで、論述・私立対策にも対応
✅朗読音声を活用し、耳からの学習も取り入れる
📌 NG行為(やってはいけない使い方)
✅インプット教材なしで、いきなり一問一答から始める → 流れを理解できず、覚えにくい
✅1周だけで終わらせる → 繰り返し演習しないとすぐに忘れる
✅既に覚えた問題と未習得の問題を区別せず、全て同じペースで解く → 非効率
✅夏に覚えて満足し、秋・冬に復習を怠る → 知識が抜け落ち、直前で焦る
📌 実際に使った受験生の声
良かった点:「スキマ時間に使いやすい」「論述対策にもなる」「音声学習が便利」
いまいちだった点:「超ハイレベル問題の取捨選択が難しい」「分厚いので持ち運びに不便」
8:最後に
『世界史 一問一答【完全版】4th edition』は、東大世界史の基礎固めや知識定着に最適な問題集です。
特に、第3問の対策として活用できるだけでなく、論述の土台となる知識を効率的に習得するのにも役立ちます。
この問題集を使いこなすためには、通史のインプットと並行して演習を行い、反復して知識を定着させることが重要です。
また、朗読音声や赤シートを活用し、スキマ時間を有効に使うことで、より効率的な学習が可能になります。
「東大世界史の得点を安定させたい」「知識の抜け漏れを防ぎたい」という受験生の皆さんにとって、本書は間違いなく強力な武器になる一冊です。
ぜひ、適切な方法で活用し、世界史の得点力を最大限に引き上げましょう!