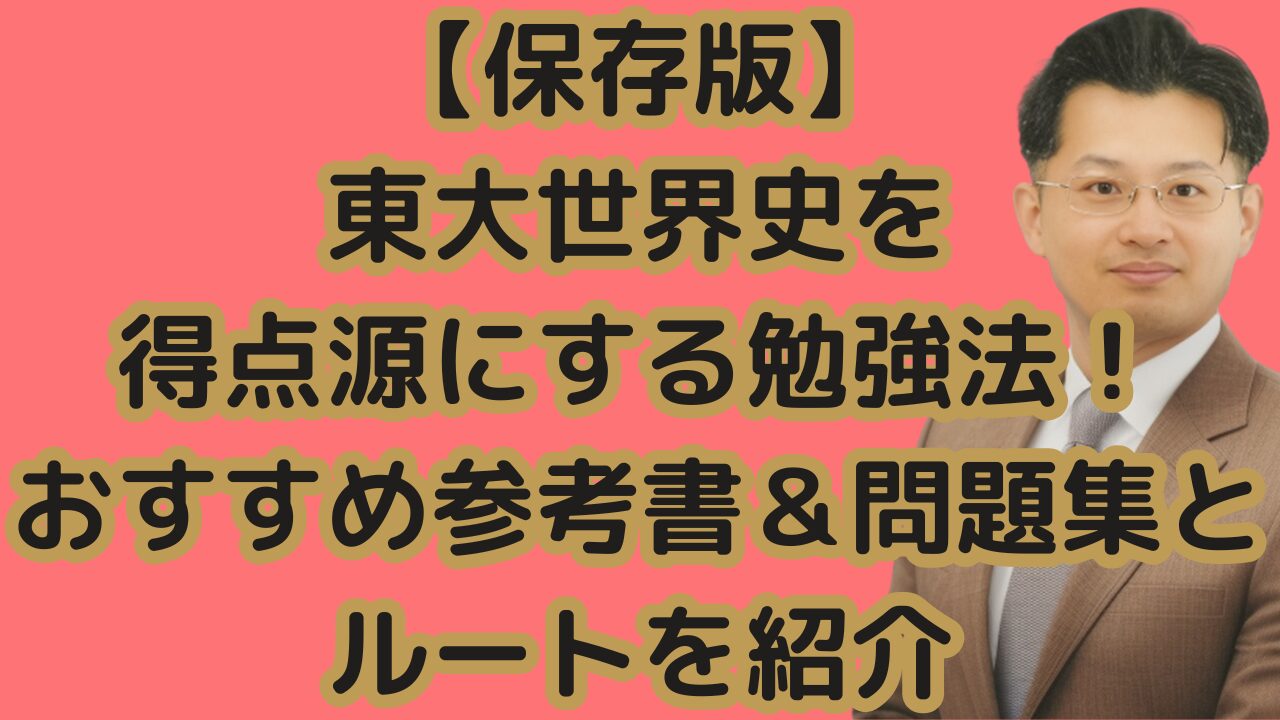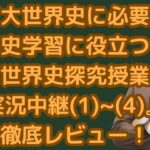東大世界史は、単なる暗記では太刀打ちできない高度な論述力と思考力を求められる試験です。
特に論述問題の比重が大きく、「どのように書けば得点できるのか?」を意識した学習が不可欠です。
「どの参考書を使えばいいの?」「論述対策ってどうすればいい?」と悩む受験生も多いでしょう。
そこで本記事では、東大世界史を得点源にするためのおすすめ参考書&問題集を厳選し、具体的な勉強法と学習ルートを徹底解説します!
適切な教材選びと戦略的な学習スケジュールで、東大世界史を確実に攻略していきましょう!
- 1はじめに:東大世界史の特徴と攻略のポイント
- 2東大世界史対策におすすめ参考書&問題集
- 3東大世界史の勉強法
- 4東大世界史の受験勉強スケジュール例
- 5東大世界史の勉強で陥りがちな罠&対策
- 6東大世界史の勉強法まとめ
- さいごに:東大世界史は「戦略的に学ぶ」ことで得点源にできる!
1はじめに:東大世界史の特徴と攻略のポイント
記述・論述中心の出題形式
東大世界史の最大の特徴は、記述・論述問題が中心であることです。
単なる知識の暗記ではなく、歴史の流れを理解し、論理的に説明する力が求められます。
✅ 第1問:大論述(500字以上)
→ 史料問題を含むことが多く、与えられた資料を適切に読み解きながら、自分の知識と結びつけて論述する力が必要。
✅ 第2問:中論述(60~120字)
→ 頻出テーマを短く簡潔に説明する問題が出題。要点を的確にまとめるスキルが問われる。
✅ 第3問:知識問題(穴埋め・一問一答)
→ 教科書レベルの基本的な用語の正確な理解が必要。
過去の出題例
・「スエズ運河完成から20年間のエジプトに対するイギリスの関与とそれに対する反発について説明せよ」(2020年)
・「1932~37年におけるイタリアの対外政策の変遷について論じよ」(2025年)
このように、地域をまたぐグローバルな視点や、歴史的背景を踏まえた説明が求められるのが東大世界史の特徴です。
必要な知識レベルと思考力
東大世界史で高得点を取るためには、以下のスキルが求められます。
① 歴史の流れを把握する力
→ 「縦の視点」(時代の変遷)と「横の視点」(同時代の各地域の動き)を理解することが重要。
→ 例:「19世紀のアジアとヨーロッパの関係の変化」「17世紀の東南アジアと西欧の交易」など。
② 同時代の各地域の動きを比較・整理する力
→ 例えば、16世紀のヨーロッパとアジアを比較しながら、大航海時代が世界に与えた影響を論じるといった問題に対応できる力が必要。
→ 『ヨコから見る世界史』を活用して、「時代ごとの世界のつながり」を整理するのが効果的。
③ 問題の要求を正しく読み取り、論述を構成する力
→ 東大の論述は、「なぜこの現象が起きたのか」「どのような影響を与えたのか」といった因果関係を問うことが多い。
→ 例えば、「産業革命が19世紀の国際関係に与えた影響を論じよ」といった問題では、経済・社会・政治の視点から構成する必要がある。
→ 『みるみる論述力がつく世界史』で論述の型を学び、添削を受けながら論述の精度を高めるのがおすすめ。
④ 知識を正確に表現する力(語句・用語の正確な使用)
→ 用語の意味を正確に理解し、適切に使い分けることが重要。
→ 例えば、「封建制」と「荘園制」の違いを正しく理解し、論述の中で正確に使うことが求められる。
→ 『世界史用語集』を活用して、用語の定義や使い方をチェックすることが有効。
⑤ 制限時間内に答案をまとめるスピードと表現力
→ 東大の試験では、日本史または地理と合わせて150分で解答しなければならない。
→ そのため、論述の構成を素早く考え、限られた時間内に的確な答案を作成する訓練が必須。
2東大世界史対策におすすめ参考書&問題集
①【通史理解に最適】『世界史探究授業の実況中継』
📌 特徴
- 実況中継形式で、まるで授業を受けているかのように学べる。
- 因果関係や背景知識が豊富で、歴史の流れがつかみやすい。
- 「授業プリント」や「年表」が付属しており、復習しやすい構成。
- 音声コンテンツがあるため、スキマ時間の学習にも活用可能。
- 教科書よりも平易な語り口で、世界史が苦手な人でもスムーズに学習できる。
②【知識の定着に】『世界史一問一答【完全版】』(東進ブックス)
📌 特徴
- 3,500問以上の一問一答を収録し、網羅性が高い。
- 頻出度が☆の数で示されており、学習の優先順位をつけやすい。
- ☆☆☆(最頻出):受験で必須レベル
- ☆☆(頻出):重要度が高い
- ☆(難関):東大・早慶などの難問対策向け
- 赤シート対応で、スキマ時間に効率よく暗記可能。
- 音声コンテンツ付きで、移動中や寝る前にも活用できる。
- 解答の補足説明が充実しており、単なる暗記ではなく背景知識も学べる。
③【横のつながりを整理】『ヨコから見る世界史』
📌 特徴
- 「時代ごとに世界全体の流れを整理」できる参考書。
- 「◯世紀の世界」や「東西文化交流」など、東大論述で問われやすいテーマを強化。
- 各地域の出来事を時代ごとに並列的に比較できる構成。
- 地図・年表・年号チェックが充実しており、視覚的に学べる。
- 別冊「ヨコのつながり暗記ブック」付きで、重要ポイントを一冊にまとめられる。
- 東大頻出の「グローバルな視点」を鍛えられるため、論述対策に最適。
④【地域史の整理に】『流れがわかる各国別・地域別世界史』
📌 特徴
- 各国・地域ごとの歴史をコンパクトに整理できる参考書。
- 東大頻出の「地域史」「海域史」(例:東南アジア・インド洋交易・地中海世界など)をカバー。
- 出来事の因果関係や影響を簡潔に整理してあり、論述の骨組み作りに最適。
- 重要用語の頻度が強調表示されており、受験に必要なキーワードがすぐわかる。
- 他の参考書では扱いが少ない海域史や交流史にも触れられている。
⑤【論述基礎を鍛える】『みるみる論述力がつく世界史』
📌 特徴
- 60字から始まり、最終的には600字の論述問題までを段階的に学べる構成。
- 「よくある答案」とその改善点を提示し、減点されやすいミスを回避できる。
- 論述の型を体系的に習得できるため、初心者にも最適。
- 設問の意図を正しく読み取る練習ができるため、論述の精度が向上。
- 東大の過去問が10題収録されており、実践的な演習も可能。
- 採点基準が明確に示されており、自己添削しやすい。
⑥【実践的な論述演習に】『判る!解ける!書ける!世界史論述』
📌 特徴
- 191問の論述問題を収録(入門・通史・テーマ史)。
- 設問の要求分析から答案作成までを体系的に学べる構成。
- 「問題の要求は?」のセクションで、設問の意図を正しく理解できる。
- 「書くべき内容をメモしてみよう」で、解答作成前に知識を整理する訓練ができる。
- 解答例だけでなく、答案の構成や採点基準に関する解説が充実。
- 東大頻出の時代・地域・テーマが網羅されており、過去問演習の前段階として最適。
⑦【過去問演習の決定版】『東大の世界史25カ年』(赤本・青本)
📌 特徴
- 25年分の東大世界史の過去問を収録し、長期的な出題傾向を把握できる。
- 解説が詳しく、論述の採点基準や答案作成のポイントが学べる。
- 東大特有の問題形式(大論述・中論述・知識問題)に慣れることができる。
- 過去問演習を通じて、論述の精度を向上させることができる。
- 最新の出題傾向に合わせるため、直近数年分は東大公式サイトなどで別途入手が必要。
⑧【知識の補強に】『詳説世界史』(山川)or『詳説世界史研究』
📌 特徴
- 『詳説世界史』(教科書):高校世界史の基本書。東大世界史のベースとなる知識を網羅する。
- 『詳説世界史研究』(発展版):教科書の内容をさらに詳しく掘り下げ、因果関係や背景を解説。
- 地図・年表・コラムが豊富で、視覚的に理解しやすい。
- 東大世界史の記述・論述問題に必要な背景知識を補強できる。
- 辞書的な使い方ができるため、過去問演習時の疑問解決に便利。
⑨【知識の正確な理解に】『世界史用語集』
📌 特徴
- 約5,200語を収録し、受験に必要な用語をほぼ網羅。
- 用語の頻度数が記載されており、重要語が一目でわかる。
- 頻度5以上の重要語は赤字で強調されているため、優先的に覚えられる。
- 簡潔な解説がついているため、語句の意味を素早く確認可能。
- 索引付きで、調べたい語句をすぐに検索できる。
- 論述問題で正確な表現をするために必須。
- 持ち運びしやすく、スキマ時間の学習に最適。
⑩【ビジュアルで流れを整理】『タペストリー』(帝国書院)
📌 特徴
- 地図・年表・図表が豊富で、視覚的に歴史の流れを理解できる。
- 政治・経済・文化の関係を時系列で整理できるため、論述の構成を考える際に役立つ。
- 世界史の重要テーマ(国際関係・宗教・交易・戦争など)が図解されている。
- 文化史の内容も充実しており、東大世界史で頻出の「思想・芸術・科学」の流れを整理しやすい。
- 時代ごとの比較がしやすい年表が掲載されており、「ヨコの視点」も強化できる。
3東大世界史の勉強法
①通史の学習
東大世界史の論述問題を解くには、まず歴史の流れをしっかり理解することが最優先です。
単なる年号暗記ではなく、因果関係・背景・影響を意識しながら通史を学ぶことが重要になります。
📖 メインで使う教材①『世界史探究授業の実況中継』
🔹使用目的
【通史の流れを把握】
📌 使い方
- 1日1~2レッスンずつ進め、流れを意識しながら読む。
- 各章ごとに「なぜこの出来事が起こったのか?」を考えながら学習。
- 重要用語をその場で覚えるのではなく、「流れの中で理解する」ことを重視する。
- 音声コンテンツを活用し、通学中やスキマ時間に復習する。
- 2周目以降は、一問一答と組み合わせながら定着を図る。
📖 メインで使う教材②『世界史一問一答【完全版】』
🔹使用目的
【知識の定着】
📌 使い方
- 『実況中継』で学んだ範囲の一問一答を解く。
- 例:「フランス革命」の章を読んだ後、その範囲の一問一答を演習。
- ☆☆☆レベルの用語を優先的に暗記し、頻出事項を完璧にする。
- 間違えた問題にはチェックをつけ、3~4周繰り返す。
- 赤シートを使い、スキマ時間に復習。
- 論述演習の際にも活用し、適切な歴史用語を選んで答案作成に活かす。
📖 参考資料とする教材『タペストリー』(帝国書院)
🔹使用目的
【ビジュアルで流れを整理】
📌 使い方
①通史学習と並行して、地図・年表を確認。
・『実況中継』の該当範囲を読む際、対応する年表や地図を参照すると理解が深まる。
②時代ごとの国際関係や経済・文化の流れを整理する。
・例:「産業革命の影響」を図解で確認し、どの国にどんな影響を与えたかを整理。
③文化史・思想史の整理に活用。
・哲学・宗教・芸術の流れを俯瞰し、論述の補強材料として活用。
②ヨコの整理(同時代の比較・関連性を把握)
東大世界史の論述では、「同時代の異なる地域の比較」や「地域間の相互関係」が頻出です。
「○世紀の世界」「東西交流」「交易ネットワーク」などのテーマを整理し、論述に活かせる知識を構築することが重要になります。
📖 メインで使う教材『ヨコから見る世界史』
🔹使用目的
【時代ごとの世界全体の流れを整理】
📌 使い方
①通史を一通り学んだ後に使用し、「時代ごとの世界のつながり」を整理する。
・例:「16世紀の世界」で、大航海時代・宗教改革・オスマン帝国の拡張などを関連づけて理解。
②過去問演習時に、「ヨコの視点」を強化するために参照。
・例:「冷戦期の各地域の動向」「産業革命が世界に与えた影響」などの論述対策に活用。
③別冊「ヨコのつながり暗記ブック」に、論述演習で得た知識をメモする。
・「19世紀の世界」など、テーマごとにまとめると知識が整理しやすい。
④赤シートを活用し、重要事項を暗記。
・世界全体の流れを俯瞰しながら、必須のキーワードを押さえる。
📖 参考資料と教材『世界史用語集』
🔹使用目的
【正確な用語の確認・補強】
📌 使い方
・『ヨコから見る世界史』で学んだ範囲の用語を確認し、定義を正確に理解する。
・例:「封建制」と「荘園制」の違い、「グーツヘルシャフト」と「農奴制」の違いを整理。
③論述問題の演習
東大世界史の論述対策では、「論述の型を習得し、実際に書く」ことが最も重要です。
論述演習を進める際は、「論述の基礎 → 実践的な演習 → 過去問演習」の流れで進めると効果的です。
📖 メインで使う教材①『みるみる論述力がつく世界史』
🔹使用目的
【論述の基礎固め】
📌 使い方
①通史学習後、論述の基礎を固める段階で使用。
・短めの論述(60~200字)から取り組み、徐々に長文論述へ進む。
②「よくある答案例」と比較し、論述の減点ポイントを理解する。
・例:「情報を詰め込みすぎている」「設問の要求とズレている」などのミスを回避。
③採点基準を意識しながら、答案を作成。
・「何を書くべきで、何を書かなくていいのか」の判断力を養う。
④段階的に文字数を増やし、論述の型を身につける。
・短文論述(60~200字)→ 中論述(200~400字)→ 長文論述(600字以上)の順に取り組む。
📖 メインで使う教材②『判る!解ける!書ける!世界史論述』
🔹使用目的
【実践的な論述演習】
📌 使い方
- 『みるみる』を終えた後に取り組み、実践的な論述演習を開始。
- 「問題の要求は?」を確認し、設問の意図を正しく読み取る練習をする。
- 「書くべき内容をメモしてみよう」で、論述の構成を考える訓練をする。
- 解答例と照らし合わせながら、自分の答案の改善点を分析。
- 添削指導を受けるか、複数の模範解答を比較して答案をブラッシュアップ。
- 過去問演習に進む前の「論述仕上げ」として活用。さまざまなテーマの論述を経験し、対応力を養う。
📖 参考資料とする教材①『詳説世界史研究』
🔹使用目的
【知識の補強】
📌 使い方
- 論述答案の根拠となる知識を深めるために活用。
- 「なぜこの出来事が起こったのか?」を説明できるようにする。
- 因果関係や背景知識を強化し、論述の説得力を高める。
📖 参考資料とする教材②『世界史用語集』
🔹使用目的
【正確な用語の確認】
📌 使い方
- 論述答案の語彙を精査し、適切な歴史用語を使用する。
- 一問一答と併用し、用語の背景知識を補強。
📖 参考資料とする教材③『タペストリー』(帝国書院)
🔹使用目的
【視覚的な整理】
📌 使い方
- 地図・年表を活用し、論述の流れを整理する。
- 特に文化史・思想史の論述問題で、変遷を把握するのに便利。
📖 参考資料とする教材④『ヨコから見る世界史』
🔹使用目的
【比較・相互関係の整理】
📌 使い方
- 「◯世紀の世界」など、同時代の地域間の関連性を整理する。
- 「東西交易」「植民地支配の影響」などのテーマ論述に活用。
📖 参考資料とする教材⑤『流れがわかる各国別・地域別世界史』
🔹使用目的
【地域史の整理】
📌 使い方
- 特定の国・地域ごとの歴史を整理するために活用。
- 国ごとの視点が求められる論述問題に対応するための知識補強。
④東大過去問演習
東大世界史で合格点を取るためには、実際の過去問を解き、東大独特の論述形式に慣れることが不可欠です。
「何年分解けばいいのか?」という疑問もありますが、理想は25年分+直近数年分の演習です。
📖 メインで使う教材『東大の世界史25カ年』(赤本・青本)
🔹使用目的
【過去問演習の決定版】
📌 使い方
①高3の9月以降に本格的に取り組む。
・それ以前に通史学習・論述演習を終えておく。
②最初の数年分は時間を気にせず、じっくり解く。
・設問の意図を分析し、解答の構成を考える練習をする。
③2回目以降は時間を測り、本番を意識した演習を行う。
・東大本番と同じ150分で、他の科目(日本史 or 地理)とセットで解く。
④解答例と比較し、自分の論述の改善点を分析。
・添削指導を受けるか、赤本・青本・予備校の模範解答と照らし合わせながらブラッシュアップ。
⑤復習時に関連するテーマの知識を補強。
・東大の論述では、単に過去問を解くだけでなく、関連する歴史背景や因果関係を深掘りすることが重要。
📖 参考資料とする教材①『詳説世界史研究』
🔹使用目的
【知識の補強】
📌 使い方
- 過去問で出てきたテーマの背景を深掘りする。
- 論述の根拠を強化するために、因果関係や影響をチェック。
- 東大世界史の記述・論述に必要な「細かい知識」や「論理的なつながり」を補強。
📖 参考資料とする教材②『世界史用語集』
🔹使用目的
【正確な用語の確認】
📌 使い方
- 論述答案の語彙を精査し、適切な歴史用語を使用する。
- 「解答の表現が曖昧になっていないか?」を確認し、修正する。
- 一問一答と併用し、背景知識を補強。
📖 参考資料とする教材③『タペストリー』(帝国書院)
🔹使用目的
【視覚的な整理】
📌 使い方
- 地図・年表を活用し、論述の流れを整理する。
- 文化史・思想史の整理に役立て、論述の補強材料として活用。
📖 参考資料とする教材④『ヨコから見る世界史』
🔹使用目的
【比較・相互関係の整理】
📌 使い方
- 「◯世紀の世界」など、同時代の地域間の関連性を整理する。
- 東大の論述で頻出の「世界的な視点」を強化する。
📖 参考資料とする教材⑤『流れがわかる各国別・地域別世界史』
🔹使用目的
【地域史の整理】
📌 使い方
- 特定の国・地域ごとの歴史を整理するために活用。
- 過去問演習で地域ごとの視点が求められる問題に対応するための知識補強。
4東大世界史の受験勉強スケジュール例
前提となる重要ポイント
東大受験では英語・数学の配点が大きく、高2のうちは英数を優先すべきです。
世界史は高3からの本格対策でも十分間に合うので、スケジュールをしっかり管理しながら効率的に進めることが重要です。
① 理想のスケジュール(余裕をもって進めるパターン)
| 時期 | 学習内容 | 使用する参考書 |
| 高2の2月~高3の5月 | 通史のインプット(2周) | 『実況中継』+『一問一答』+『タペストリー』 |
| 高3の6月 | ヨコの整理(同時代の比較) | 『ヨコから見る世界史』+『世界史用語集』 |
| 高3の7月・8月 | 論述の基礎固め(短めの論述から) | 『みるみる論述力がつく世界史』 『判る!解ける!書ける!世界史論述』 |
| 高3の9月~入試 | 東大世界史の過去問演習・仕上げ | (『判る!解ける!書ける!世界史論述』)+『東大世界史25カ年』+各参考資料+『一問一答』 |
📌 このスケジュールの特徴
✅ 通史を先に固めてから論述演習に入るので、知識の抜けが少ない。
✅ ヨコの整理を通して、「同時代の世界のつながり」を意識できる。
✅ 論述演習を2か月間確保し、答案作成の技術を磨く時間がある。
✅ 9月以降は過去問演習に集中できるため、東大の傾向を徹底的に対策可能。
⚠ 注意点
- 通史学習をダラダラやると6月以降の計画に支障が出るため、通史学習は特に計画的に進めることが重要。
- 論述演習を始める前に、基礎知識の抜けをなくしておくこと。
- 過去問演習に入ったら「解くだけ」にならず、復習・知識補強を徹底すること。
② 夏休みに追い上げるパターン(スタートが遅れた場合)
| 時期 | 学習内容 | 使用する参考書 |
| 高3の6月・7月 | 通史のインプット(圧縮学習) | 『実況中継』+『一問一答』 |
| 高3の8月 | ヨコの整理+論述の基礎固め | 『ヨコから見る世界史』+『みるみる論述力がつく世界史』 |
| 高3の9月・10月 | 本格的な論述演習 | 『判る!解ける!書ける!世界史論述』 |
| 高3の11月~入試 | 東大世界史の過去問演習・仕上げ | 『東大世界史25カ年』+各参考資料+『一問一答』 |
📌 このスケジュールの特徴
✅ 夏休みの学習量を増やし、短期間で通史を固める。
✅ 8月にヨコの整理と論述演習を同時に行い、効率よく進める。
✅ 9月から本格的に論述対策を行い、過去問演習の準備を整える。
⚠ 注意点
- 夏休みの勉強時間を確保しないと、通史理解が中途半端になり、その後の論述演習に影響が出る。
- 8月の「ヨコの整理+論述演習」をスムーズに進めるために、1日最低3時間は世界史に充てる。
- 論述演習の時間が短くなるため、復習を徹底し、アウトプットを意識すること。
③ 他の教科の負担が大きく、世界史に時間を割けないパターン(最低限の対策)
| 時期 | 学習内容 | 使用する参考書 |
| 高3の6月~8月 | 通史のインプット(最低限の学習) | 『実況中継』+『一問一答』 |
| 高3の9月~12月 | 論述の基礎固め(最低限の演習) | 『みるみる論述力がつく世界史』+『判る!解ける!書ける!世界史論述』 |
| 高3の1月・2月 | 東大過去問演習(直前対策) | 『東大世界史25カ年』 |
📌 このスケジュールの特徴
✅ 通史のインプットをコンパクトにまとめ、他教科とのバランスを考慮。
✅ 論述演習の時間が少ない分、必要最低限の問題を厳選して取り組む。
✅ 直前期に過去問演習を集中させ、最短ルートで合格点を狙う。
⚠ 注意点
- 通史のインプットを1周で終わらせるのではなく、最低でも2周すること。
- 論述演習が不足しがちなので、過去問演習時に復習を徹底し、論述の精度を高める。
- 直前期に詰め込みすぎると負担が大きくなるため、計画的に進めること。
💡どのスケジュールを選ぶべきか?
| 受験生の状況 | おすすめのスケジュール |
| 世界史にしっかり時間を割ける受験生 | ① 理想のスケジュール |
| 高3のスタートが遅れたが、夏に集中して勉強できる受験生 | ② 夏休みに追い上げるパターン |
| 他の科目の負担が大きく、世界史の勉強時間を確保しにくい受験生 | ③ 最低限の対策パターン |
✅ 東大世界史のスケジュール管理のポイント
①通史を早めに終わらせ、9月以降の過去問演習に余裕をもたせる!
・「知識不足で論述が書けない」状態を避けるために、通史は高3の前半で固める。
②ヨコの整理を入れ、比較論述に対応できる力をつける!
・東大の論述では、時代ごとの「世界全体の動き」を問う問題が頻出。
③論述演習は「型を身につける → 実践する」の流れで進める!
・『みるみる』→『判る!解ける!書ける!』→過去問演習の順で鍛える。
④過去問演習では、解いた後の復習を重視!
・「ただ解く」だけではなく、用語集や詳説世界史で背景知識を補強する。
5東大世界史の勉強で陥りがちな罠&対策
東大世界史は、単なる暗記ではなく、論述力や思考力が求められる試験です。
そのため、「とにかく暗記」や「過去問を解くだけ」では十分な得点を取れません。
ここでは、東大世界史の勉強で陥りがちなミスと、その対策を解説します!
❌ 罠①:通史を学ばずに論述演習を始めてしまう
📌 よくある失敗
- 通史が曖昧なまま論述を解こうとして、全く書けない…
- 用語を知っていても、時代の流れがわからず論述の構成ができない…
- 過去問を解いても、背景知識が足りずに不完全な答案になってしまう…
✅ 対策
まずは通史を固める!
✔ 『実況中継』+『一問一答』で通史の流れをインプット。
✔ タペストリーを活用し、歴史をビジュアルで整理。
✔ 「なぜこの出来事が起こったのか?」を意識しながら学習する。
✔ 通史がある程度固まったら、短めの論述(60~120字)から練習を始める。
❌ 罠②:「とにかく一問一答!」で丸暗記に頼る
📌 よくある失敗
- 用語は覚えているのに、論述を書こうとすると知識をうまく活かせない…
- 一問一答の答えを丸暗記しているだけで、背景知識が頭に入っていない…
- 「この出来事の背景は?」と聞かれると答えられない…
✅ 対策
背景知識とセットで覚える!
✔ 『世界史用語集』を活用し、用語の意味や背景を確認。
✔ 『ヨコから見る世界史』で、同時代の地域間の関係を整理する。
✔ 論述問題を解く際、一問一答の知識を「どう使うか?」を考える練習をする。
❌ 罠③:論述の「型」を学ばずに、いきなり長文論述を書こうとする
📌 よくある失敗
- 「とりあえず書いてみたけど、何をどう書けばいいのかわからない…」
- 「構成を考えずに書き始めたら、話がズレてしまった…」
- 「長文を書くのがつらくて、論述対策が嫌になった…」
✅ 対策
論述の型を学んでから書く!
✔ まずは『みるみる論述力がつく世界史』で、短い論述から練習。
✔ 「よくある答案例」と模範解答を比較し、どこがダメなのかを理解する。
✔ 『判る!解ける!書ける!世界史論述』で実践演習を行い、構成力を鍛える。
❌ 罠④:論述の添削を受けずに自己流で進める
📌 よくある失敗
- 「論述を書いたけど、これで本当に点が取れるのかわからない…」
- 「解答例と比べて、自分の答案が何がダメなのか分からない…」
- 「なんとなく書いているけど、減点されるポイントが分からない…」
✅ 対策
論述は「添削」が超重要!
✔ 学校や塾の先生に添削してもらう。
✔ 予備校や模試の添削を活用したフィードバックをもらう。
✔ 独学の場合、模範解答と比較し、採点基準を意識しながら自己添削を行う。
❌ 罠⑤:過去問演習を「解くだけ」で終わらせてしまう
📌 よくある失敗
- 「25年分の過去問を解いたのに、なぜか点数が伸びない…」
- 「過去問を解くだけで、復習が雑になってしまった…」
- 「同じような問題が出ても、また失点してしまう…」
✅ 対策
過去問は「復習」が命!
✔ 間違えた問題は、『詳説世界史研究』や『世界史用語集』で背景を調べる。
✔ 論述の構成を見直し、改善点を記録する。
✔ 「なぜこのテーマが出題されたのか?」を考え、次に活かせるようにする。
❌ 罠⑥:世界史ばかりに時間をかけすぎて、他教科が疎かになる
📌 よくある失敗
- 「世界史の勉強が楽しくて、英語や数学の勉強時間が足りなくなった…」
- 「論述に時間がかかりすぎて、他の科目の対策が間に合わない…」
- 「世界史の得点は伸びたけど、総合点が足りずに不合格に…」
✅ 対策
世界史と他教科のバランスを取る!
✔ 1日の勉強時間を管理し、世界史にかける時間を調整する。
✔ 英語・数学の配点が大きいので、優先順位を決めて学習する。
✔ 世界史の論述対策は、計画的に進めて時間を効率的に使う。
6東大世界史の勉強法まとめ
✅ 東大世界史で高得点を取るための戦略
1️⃣ 通史を固める(高3の5月までに完了)
👉 『実況中継』+『一問一答』+『タペストリー』を活用し、歴史の流れを把握することが最優先!
2️⃣ ヨコの整理を行う(高3の6月)
👉 『ヨコから見る世界史』+『世界史用語集』で、「時代ごとの世界全体の動き」を整理!
3️⃣ 論述演習を段階的に進める(高3の7~8月)
👉 『みるみる論述力がつく世界史』で短文論述を練習 →『判る!解ける!書ける!世界史論述』で長文論述へ
4️⃣ 過去問演習を通じて実戦力をつける(高3の9月~入試)
👉 『東大の世界史25カ年』+『詳説世界史研究』+『用語集』を活用しながら復習を徹底!
✅ 東大世界史の得点力を最大化するためのポイント!
📌 通史の流れをしっかり理解する(単なる暗記ではなく、因果関係を意識!)
📌 ヨコの視点を持ち、同時代の地域間の関係を整理する
📌 論述の「型」を学び、論理的な答案を作成できるようにする
📌 過去問演習を解くだけで終わらせず、復習・分析を徹底する
📌 世界史だけでなく、英語・数学などの他教科とのバランスも考える
さいごに:東大世界史は「戦略的に学ぶ」ことで得点源にできる!
東大世界史では、「正しい参考書・問題集を使い、適切な順序で学習を進めること」が高得点を獲得するためのカギです。
「通史の完成 → ヨコの整理 → 論述演習 → 過去問演習」の流れを意識し、計画的に進めましょう!