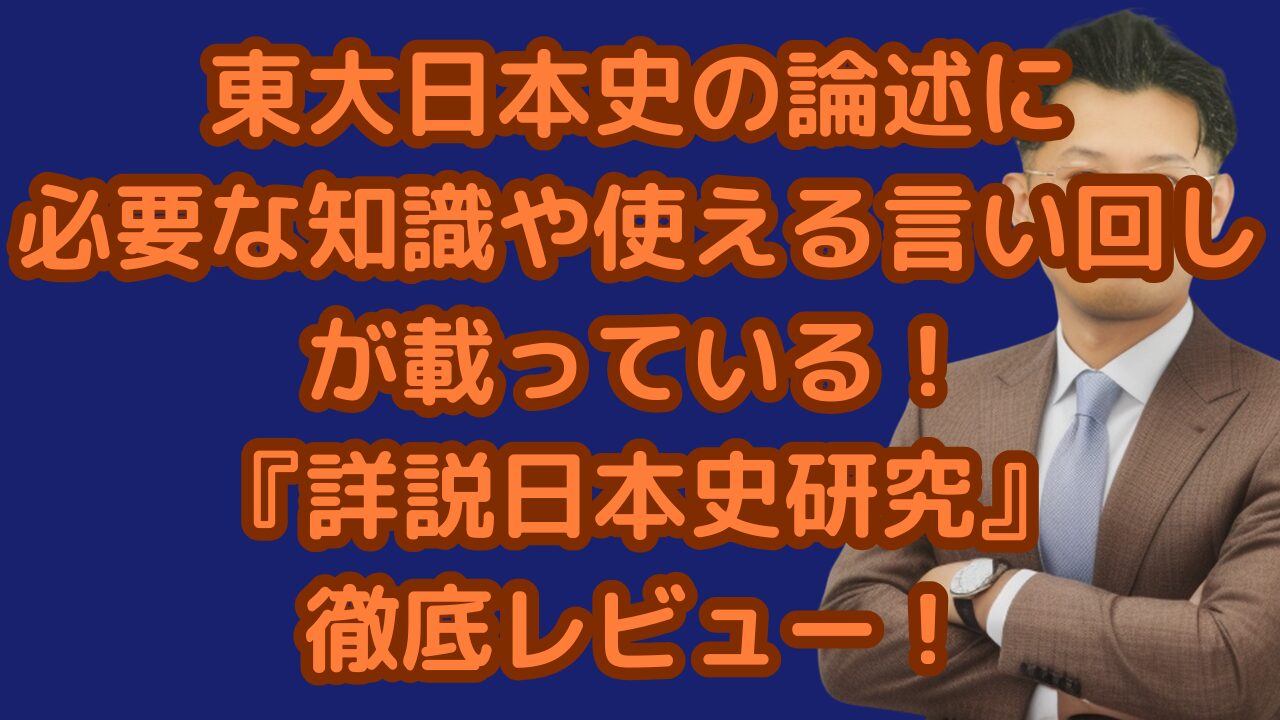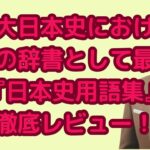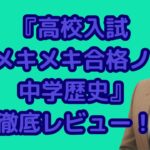「東大日本史の論述、知識はあるはずなのに点が伸びない…」
「過去問の解説を読んでも、“なぜそう書くのか”がイマイチ分からない…」
そんな悩みを抱える東大志望の受験生にぜひ使ってほしいのが、山川出版社の『詳説日本史研究』です。
教科書『詳説日本史』に完全準拠しつつ、圧倒的な情報量で日本史を深く掘り下げてくれる一冊です。
しかも、執筆者のうち8名が東京大学の教授や名誉教授という、東大論述との親和性が非常に高い参考書です。
「なぜその出来事が起こったのか?」「どんな因果関係があったのか?」といった、東大日本史で得点に直結する“深い理解”を得るための最強の「辞書」として活用できます。
この記事では、そんな『詳説日本史研究』の魅力・使い方・注意点を東大志望者目線で徹底解説します!
使いこなせば、あなたの論述は一段と説得力を増すはずです!
1:『詳説日本史研究』とは
『詳説日本史研究』は山川出版社の教科書『詳説日本史』に準拠した、最も情報量の多い日本史の本格派参考書です。
特に東大日本史のように、「なぜその出来事が起こったのか」「どうしてそうなったのか」といった背景や因果関係まで求められる論述試験において極めて有用な一冊です。
基本情報
| 項目 | 内容 |
| 編者 | 佐藤信・五味文彦・高埜利彦・鳥海靖 |
| 執筆者 | 加藤陽子、倉本一宏、五味文彦、桜井英治、佐々木恵介、佐藤信、設楽博己、白石太一郎、高埜利彦、鳥海靖、藤田覚、本郷和人、山形眞理子 |
| 出版社 | 山川出版社 |
| 発売日 | 2017年8月31日 |
| 定価 | 2,750円(税込) |
| ページ数 | 566ページ |
基本構成
本書は、時代ごとの4部構成で、原始から現代までの日本史を徹底的に解説しています。
教科書では省略されがちな背景や因果関係まで丁寧に記述され、地図・史料・図解も豊富に掲載されています。
まさに“論述に強い”日本史理解を支えるための、受験生向けの最上級インプット教材です。
- 第1部:原始・古代
- 第2部:中世
- 第3部:近世
- 第4部:近代・現代
単なる知識の羅列ではなく出来事の「つながり」を理解することで、東大論述に不可欠な“深い思考力”を養うことができます。
2:『詳説日本史研究』の使用タイミングと使用目的
使用タイミング
『詳説日本史研究』を最も効果的に使えるのは、東大日本史の過去問演習に取り組んでいるときです。
論述問題を実際に解いてみると、「知識はあるつもりだったけど、背景や因果があやふや…」「どんな表現で書けばいいか迷う…」といった壁に直面することが少なくありません。
そんなときに本書を辞書代わりに使えば、論述に必要な知識の補強だけでなく、“東大的な視点”での理解の深掘りができます。
使用目的
- 解いた論述問題の論点や背景知識を確認する
- 論述答案に必要な因果関係・経緯・意義などの要素を補強する
- 実際の記述で使えるような表現や文構成をインプットする
特に、「表現の引き出しが少ない」「答案が浅く見えてしまう」と悩んでいる人は、本書を通じて“論述で使える日本史の語彙や言い回し”を蓄えることが大きな武器になります。
3:『詳説日本史研究』の特徴とメリット
圧倒的に詳しい解説で「なぜ?」が分かる!
本書は山川出版社の教科書『詳説日本史』に準拠しつつ、その数倍の情報量で背景・因果関係・流れを丁寧に説明してくれるのが最大の特長です。
「○○の改革が行われた背景には何があったのか?」「なぜその政策が失敗したのか?」といった、論述で高得点を取るために不可欠な“深い理解”が、自然と身につきます。
東大論述でそのまま使える表現が身につく!
論述で使える語彙・言い回し・構文が本文中に自然に登場するため、答案作成に使えるフレーズのストックがどんどん増えていきます。
「この本に載ってないなら、いらない」くらいの安心感!
膨大な知識量をカバーしているため、「この本に書いてないなら、東大日本史に出る可能性は極めて低い」と割り切れるほどの網羅性があります。
執筆陣の半数以上が東大関係者!
執筆者13名のうち、実に8名が東大の教授・名誉教授・元教授という驚異の布陣です。
つまり、「東大が求める日本史の視点・学び方」が反映された参考書なのです。
4:『詳説日本史研究』の効果的な使い方
『詳説日本史研究』は、“辞書のように使う”のがもっとも効率的かつ実践的な活用法です。
特に、東大日本史の過去問演習と組み合わせて使うことで、その真価を発揮します。
📘 Step 1:過去問を解く
まずは、東大日本史の過去問に実際に取り組んでみましょう。
書いてみると、「あれ、この出来事の背景ってなんだっけ?」「この政策の影響って…?」というモヤモヤが出てくるはずです。
📘 Step 2:『詳説日本史研究』で該当部分を調べる
そのモヤモヤ=不明点・曖昧な部分を、本書を使ってピンポイントで確認します。
用語の意味だけでなく、その背景や因果関係、位置づけまで詳しく書かれているので、理解が一気に深まります。
📘 Step 3:論述で使える知識として「吸収」する
調べた内容は“その場しのぎ”で終わらせず、使える知識としてストック&覚えることが重要です。
必要に応じてノートにまとめたり、表現を写したりすることで、次回以降の論述に生かせるようになります。
▶ ポイントは、“読む”のではなく“調べて覚える”という意識で使うこと!この使い方を徹底すれば、論述の完成度が確実にワンランク上がります。
5:『詳説日本史研究』の使用上の注意点
『詳説日本史研究』は情報量の多さと深さが魅力の一方で、使い方を間違えると逆効果になることもあります。
以下のポイントには注意しておきましょう。
注意①:通読には向かない!辞書的に使うのが正解
本書は説明が非常に詳しく、文章も教科書的で硬めです。
そのため、「最初から最後まで通読しよう!」とすると、内容の重さとボリュームに圧倒されて挫折する可能性大です。
▶ 基本は“ピンポイントで調べる用”として活用するのがベストです。
注意②:資料読み取り型の論述にはこれだけでは不十分
東大日本史の論述では、「資料を読み取り、それを根拠に答える」タイプの問題が頻出です。
本書に書いてある知識だけをベースに論述を組み立てると、資料とのズレが生じ、高得点が狙えない可能性があります。
▶ 資料の読み取りを含む問題の論述を書く際は、この本の知識を補助的に使うことが大切!
注意③:新課程(日本史探究など)には対応していない
本書の出版は2017年と少し前なので、新課程で導入された「日本史総合」や「日本史探究」には非対応です。
ただし、東大の出題傾向自体は大きく変わっていないため、東大論述対策としては現在も十分に有用です。
▶ 最新のトピックや視点が必要な場合は、資料集や新課程対応の教材で補いましょう。
6:『詳説日本史研究』を実際に使った受験生の声
良かった点
🗣「東大の論述って、“なぜ?”をちゃんと説明できないと点にならないけど、この本には背景とか因果関係がめちゃくちゃ詳しく書いてあって、本当に助かった!」(高3・文一志望)
🗣「地味にありがたいのが表現。論述でよく使う言い回しがそのまま載ってるから、答案に使える語彙が増えた感じ!自分の答案がちょっと“東大っぽく”なった気がする(笑)」(既卒・文三志望)
🗣「調べたことが全部載ってるから、安心感がハンパない。過去問やってて『このテーマ出たら終わる…』って思っても、この本で調べるとすぐ対応できた!」(高3・文二志望)
いまいちだった点
🗣「最初に通読しようとしたけど、情報多すぎて断念…。あれは“読む”ってより“調べる”用だなって途中で気づいた(笑)」(高2・文一志望)
🗣「内容はすごいんだけど、東大の論述って資料が超大事じゃん?この本に書いてあることだけで答案組み立てると、資料とズレて失点する感じがあった」(高3・文三志望)
🗣「2017年出版だから、探究対応ではないんだよね。まあ東大には十分だけど、ちょっと新しめの視点とかは資料集とかで補う必要あるかも」(高3・文三志望)
7:『詳説日本史研究』の記事のまとめ
- 山川の教科書『詳説日本史』に準拠した、最も詳しい日本史参考書
- 背景・因果関係・経緯・意義など、論述に必要な深い知識が得られる
- 東大論述で使える表現・語彙を自然にストックできる
- 東大教授・名誉教授など執筆陣の8名が東大関係者という安心感
- 過去問演習時に辞書的に使うのが最も効果的な活用法
- 通読には向かず、調べて使うスタイルが基本
- 2017年出版のため、新課程には非対応だが、東大対策としての価値は依然高い
8:さいごに
『詳説日本史研究』は、東大日本史の論述対策における“最強の知識辞典”ともいえる存在です。
単なる暗記ではなく、「なぜその出来事が起こったのか」「どう影響したのか」といった論述で得点を左右する“背景理解”や“因果のつながり”をしっかり身につけることができます。
もちろん、文章量は多く、読みやすさでは他の参考書に劣る部分もあります。
しかし、「論述であと一歩深みが足りない」「答案に説得力が出ない」と悩んでいる受験生にとっては、圧倒的に頼れる一冊です。
使い方のポイントは「必要なときに、必要な部分だけを調べる」ことです。
東大の論述問題と向き合いながら、本書を“知識の引き出し”として活用すれば、あなたの答案は確実に変わります。
本気で東大合格を目指すあなたにこそ、『詳説日本史研究』を使ってほしいと思います!