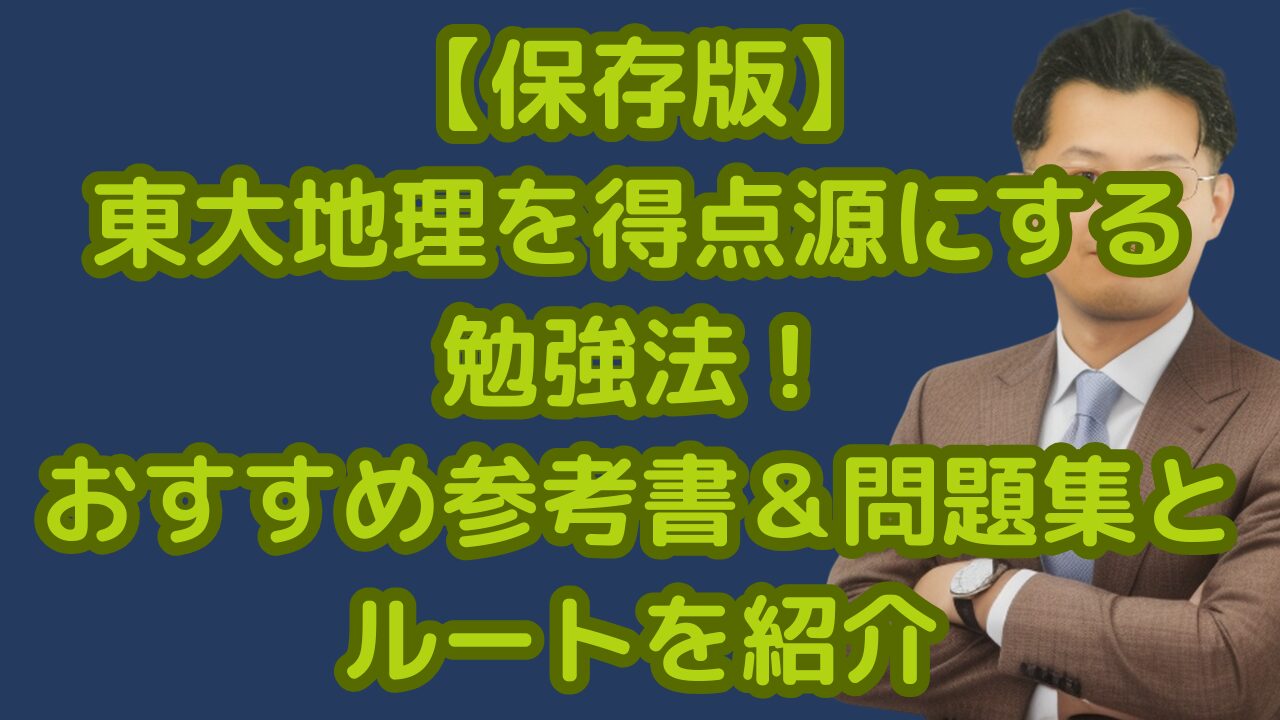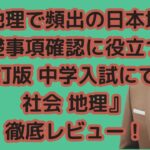「地理って暗記科目じゃないの?」
「論述問題ばっかりで、どう対策すればいいのか分からない…」
そんな不安を感じている東大志望者は少なくありません。
東大の地理は、他大学の地理とは一線を画します。
単なる知識の暗記ではなく、「背景まで含めた理解」と「地理的思考力」が問われる記述中心の出題形式です。
しかも、時事問題や日本の地誌など、幅広いテーマに対応する柔軟さも求められます。
でも、逆に言えば――
対策次第で、地理は「伸ばしやすく、差をつけやすい科目」でもあるのです。
本記事では、東大地理を得点源に変えるための
【参考書・問題集の使い方】【学習ルート】【スケジュール例】まで、東大指導のプロ視点で徹底解説!
「何から始めればいいのか分からない」という地理初学者にも、「地理は一通りやったけど論述に自信がない」という上級者にも役立つ保存版の内容です。
- 1.はじめに:東大地理の特徴と攻略のポイント
- 2.東大地理のおすすめ参考書&問題集
- 3.東大地理の勉強法
- 4.東大地理の受験勉強スケジュール例
1.はじめに:東大地理の特徴と攻略のポイント
東大の地理はいわゆる“知識偏重型”の地理とは異なり、思考力・表現力・時事対応力をバランスよく求められる、極めて「地理らしい」地理です。
以下に、主な特徴を整理してみました。
① 論述問題の出題が多い(30~90字記述が基本)
共通テストのようなマーク式ではなく、1~3行(30~90字)程度の記述問題が中心。
与えられた資料やテーマに対して、自分の言葉で「なぜそうなるのか」を説明する力が問われます。
単なる知識の確認ではなく、知識を論理的に使いこなすスキルがカギです。
② 単なる暗記ではなく、「背景」や「関連性」を問う
東大地理では、「この用語を知っているか?」ではなく、「この現象がなぜ起きるのか?」「その背景には何があるのか?」といった因果関係の理解が必須です。
例えば、
- 農産物の産地 → “なぜその地域で栽培されているのか?”
- 人口の都市集中 → “どんな社会・経済的背景があるのか?”
こうした「知識を使った説明」が得点に直結します。
③ 時事的なテーマを扱う問題が多い
「SDGs」「エネルギー問題」「人口移動」「ファストファッション」「災害と地域」など、
現代社会の課題と地理を結びつけた出題も年々増加中です。
ニュースや時事ワードを「地理的視点」で解釈できる力が試されます。
④ 日本の地誌に関する出題が目立つ
東大地理では、「地域の特徴」を論じさせる問題も頻出です。
とくに日本の地誌(各地方の気候・産業・交通・人口動態など)については、“知識+考察”が求められる重要分野です。
たとえば「東京都でブルーベリー栽培が盛んな理由は?」など、具体的な地域を題材にした記述問題が出題されやすくなっています。
2.東大地理のおすすめ参考書&問題集
では、そうした特徴の東大地理の対策のためにどんな参考書、問題集を使えばいいのか、以下に東大対策のプロが考えるおすすめの教材を紹介していきます。
①『改訂版 中学入試にでる順 社会 地理』
●特徴
『でる順 社会 地理』は中学入試で頻出の日本地理テーマを「出る順」に整理し、要点と演習がセットで学べる超効率型の教材です。
ページ構成はシンプルで、1テーマ=見開き2ページです。
左で要点整理、右で問題演習という流れでテンポよく進められます。
特に東大地理においては「日本の地誌」に関する出題が多いため、本書のような都道府県ごとの特色・気候・産業・交通などを総整理できる教材は非常に価値があります。
また、難関中学入試で実際に出題された図表や統計資料を使った問題も収録されており、地理的な資料の読み取り力も自然と鍛えられます。
●使い方
- 学習初期に、日本地誌の土台を短期間で整える目的で使うのがベストです。
- 特に「中学時代にあまり地理をやっていない」「高校地理に入る前に、日本の地域ごとの特色をざっくり思い出しておきたい」という受験生に最適。
- 1日3~5テーマペースで進めれば、2~3週間で一周できます。
- 過去問演習で「日本地理の知識が浅い」と感じたときの弱点補強教材としても再活用できます。
地理が苦手な人ほど、「地理=知識がバラバラでよく分からない…」という印象を持ちがちですが、本書を使って都道府県・地方単位で知識を整理すると一気に視界がクリアになります。
②『高校入試 実力メキメキ合格ノート 中学地理』
●特徴
『高校入試 実力メキメキ合格ノート 中学地理』は、中学地理の全範囲をやさしく・網羅的に復習できる講義形式の参考書です。
特徴はなんといってもその読みやすさと整理力です。
話し言葉ベースの解説で、「地理が苦手でもスラスラ読める」構成になっており、ビジュアル(地図・図表・写真)も豊富で、知識が自然と頭に入ります。
- 地域ごとの気候・産業・交通を一望できる「地域別まとめ」
- 統計や緯度・経度・地図記号などの資料系の基礎項目も網羅
といったパートも充実しており、高校地理への橋渡しとして最適な設計です。
●使い方
- 高校地理に入る前の「本当のゼロスタート」からでも無理なく取り組めるのが最大の強み。
- 1日1~2単元(10~15分)を目安に読み進め、週末に巻末まとめで総整理。
- 『村瀬のゼロからわかる地理B』が難しく感じた人は、本書で「リスタート」するのがおすすめ。
- また、「知識の定着」を図る整理ノート(書き込み式)もついており、アウトプット型の復習にも対応。
特に、地図や気候の基本など東大の論述でも狙われやすいテーマを「何も見ずに説明できるか?」を意識しながら進めましょう。
こうした知識は、東大地理の「日本地誌論述」や「統計・グラフ読み取り問題」のベースになります。
③『村瀬のゼロからわかる地理B 系統地理編・地誌編』
●特徴
『村瀬のゼロからわかる地理B』は、村瀬哲史先生による、「理解して覚える」ことを徹底的に重視した地理参考書です。
2冊構成になっており、
- 「系統地理編」:地形・気候・産業などテーマ別に地理現象の“なぜそうなるのか”を解説。
- 「地誌編」:世界や日本の各地域ごとに、自然・産業・文化などの地理的特徴を整理。
文章は講義形式でわかりやすく、「板書風のまとめ」や「図・地図・写真・グラフ」も豊富です。
統計や地理現象の因果関係を論理的にイメージできるようになるのが最大の強みです。
●使い方
- 地理学習の初期に、理解中心で知識をインプットする教材として活用。
- 1テーマ30分~45分程度で読み進め、読んだ後は「要点」をノートにまとめると記憶に残りやすい。
- 読むだけでなく、「なぜそうなるか」を図や言葉で説明できるようにするのがポイント。
- 過去問演習や論述問題に挑戦した後、「このテーマをもう一度確認したい」と思ったときの“調べる辞書”としても非常に便利。
④『地理一問一答【完全版】3rd edition (東進ブックス 一問一答)』
●特徴
『地理一問一答【完全版】3rd edition』は、系統地理・地誌の重要語句5000問以上を一問一答形式で整理した圧倒的ボリュームの問題集です。
構成は次のように整理されており、
- 第1〜4部:系統地理(自然環境・産業・人口・都市・文化など)
- 第5部:地誌(日本・世界の各地域)+白地図問題
- 各章末にはステップアップ問題(発展レベル)も掲載
また、用語には頻出度を示す★印がついており、
- ★★★ … 必須レベル
- ★★ … 主要国立・私大レベル
- ★ … 難関私大レベル
という形で、「どこまで覚えるべきか」の取捨選択がしやすい設計になっています。
●使い方
- 『村瀬のゼロからわかる地理B』などでインプットした後、知識の定着確認・復習用に使用。
- 通学中や隙間時間に赤シートで確認すれば、短時間でも効率よくアウトプットが可能。
⑤『新詳 資料地理の研究』
●特徴
『新詳 資料地理の研究』は帝国書院が発行する論述型入試向けに特化した資料集であり、
図表・統計・写真などの視覚資料とその背景説明がセットになっているのが最大の特徴です。
- 地形・気候・産業・文化・人口・都市・グローバル化など、系統地理をテーマ別に整理
- 各章には「なぜこの現象が起こるのか?」を解説する地理的背景付き
- 豊富な図表資料⇒単なる羅列ではなく論理的に説明する力を育てる構成
「この統計を見てどう読み取るか?」「このグラフの背景にある社会的要因は何か?」といった視点でまとめられており、東大の論述問題に必要な“思考の道筋”をトレーニングできる資料集です。
●使い方
- 基礎学習(村瀬、東進一問一答)を終えた後の知識整理・応用期に使用。
- 論述問題や過去問に取り組む際に、「このテーマ、背景をもっと深く知りたい」と思ったら本書で確認。
- 青本や過去問の解説で不明な論点が出てきたとき、「辞書」のように使って即調べられる。
- 統計・図表・写真は「どこが問われそうか?」という視点でチェックし、論述に使える要素をメモしておく。
「背景説明が書けずに減点されがち」「知識はあるけど論述になると手が止まる…」という人にとって、本書はまさに「論述の土台を完成させるツール」になります。
⑥『新詳地理資料 COMPLETE』&『図説地理資料 世界の諸地域NOW』
●特徴
この2冊は、帝国書院が発行する最新の地理資料集であり、
- 『新詳地理資料 COMPLETE』:系統地理の全分野を網羅したデータ&図表資料集
- 『図説地理資料 世界の諸地域NOW』:地誌(各地域の自然・文化・産業など)に特化
というように、役割が明確に分かれた構成となっています。
共通の特長は以下のとおりです。
- 最新の統計データ、地図、写真、模式図が超豊富
- 時事トピック(ウクライナ侵攻、SDGs、能登半島地震など)にも対応
- 「巻頭特集」「NOWページ」「現地レポート」など、東大的な出題に直結するリアルな情報が多数
さらに、『新詳地理資料 COMPLETE』では「GIS」「都市の拡大と交通」など地理探究で重視されるテーマが強化されており、『図説NOW』では、世界各地の自然環境→歴史→文化→経済→現代的課題という“ストーリー構成”で知識が整理できます。
●使い方
- 過去問演習・論述演習中に、辞書的に使うのが基本。
- 「このテーマ、最新のデータどうなってる?」
- 「この地域の文化や経済背景って何が特徴だったっけ?」
- テーマごとに興味があるページを拾い読みする“読み物”としても使える。
- 「共通テストや他大学対策にも活用できる」ほど情報量が豊富だが、東大に特化する場合は必要なテーマに絞って活用するのが◎。
特に、時事性のある地理現象(例:観光地のオーバーツーリズム、エネルギー政策の変化)に対応できるのはこの2冊の強みです。
また、視覚情報が多くインプットしやすいため、“通読ではなく、気になったときに開く・見る”という使い方が一番効果的です。
⑦『瀬川&伊藤のSuper Geography COLLECTION 01 大学入試 カラー図解 地理用語集』
●特徴
『瀬川&伊藤の地理用語集』は、大学入試用に特化したカラー図解付きの地理用語辞典です。
- 収録語数は約3,400語。入試頻出語から最新の時事キーワードまでカバー。
- 全項目にわかりやすい図解・写真・グラフ付き → 視覚的に理解しやすい!
- 語句には「青チェック(共通テスト)」「オレンジチェック(国公立二次)」「赤チェック(私大)」と学習レベルが明示されており、効率よく対策可能
- 解説文の要点は太字となっており、読みにくさゼロ
●使い方
- 『村瀬』『地理一問一答』などで学んだ語句の中で「この意味ちょっと曖昧だな…」と感じたら即チェック!
- 論述答案の作成中に、「もっと適切な言葉や言い回しないかな?」というときの表現のストック源として使える。
- 特にオレンジチェック(国公立二次レベル)語を優先的に覚え、論述で自然に使えるようにするのがコツ。
- テーマごとに見開きで整理されているため、「同じジャンルの語句」をまとめて確認でき、記憶が定着しやすい。
「論述にふさわしい語彙が少ない」「答案が説明不足で浅くなりがち」と感じている人ほど、
この用語集を辞書代わりに使って、表現の引き出しを増やすのがおすすめです。
⑧『マンガでわかる!中学入試に役立つ教養 地理153』
●特徴
『マンガでわかる!地理153』は、時事問題と地理の接点をマンガ形式でわかりやすく解説した参考書です。
- 「都市のスポンジ化」「モーダルシフト」「スマート林業」など、ニュースでよく聞くけどイメージしづらい用語が、マンガ+図解でスッと理解できる
- 1語1〜2ページ構成で、テンポよく読み進められる
- マンガで直感的に理解 → 特集ページで背景知識を深掘りする“二段階構成”
- SDGsや人口問題、交通、エネルギー、災害など、東大で実際に出題されたテーマと高い一致率を誇る
特に、「視覚的に覚えたい」「活字が苦手」「ニュースの背景がよく分からない」といった受験生にぴったりな一冊です。
●使い方
- 時事問題の対策が必要と感じたタイミングで、辞書的にピックアップして読む。
- 「ニュースで聞いた言葉が東大地理にどう関係するか?」という視点で、マンガ→特集の順に読むのが効果的。
- 過去問演習で知らないテーマが出てきたとき、「関連ワードがないか?」を索引から探してすぐ確認。
- 1語あたり2〜3分で読めるので、通学中・寝る前などにちょこちょこ読めるのも大きなメリット。
「難しいことを簡単に、面白く覚えたい」という人には、まさに東大時事対策の“入り口”として最適な教材です。
⑨『マンガでわかる!中学入試に役立つ教養 政治・国際164』
●特徴
『マンガでわかる!政治・国際164』は、政治・経済・国際関係・環境問題などを地理と絡めて理解するためのマンガ形式参考書です。
- 「SDGs」「ファストファッション」「テレワーク」「気候変動」「海洋プラスチック」など、東大で出題されたテーマが多数収録
- 各項目はマンガ1〜2ページ+特集ページで構成され、読みやすさと情報量を両立
- 現代の社会課題とその背景、地理的なつながりを図やイラストで直感的に理解可能
- 教科書や定番資料集ではフォローしきれない“最新の話題”にもしっかり対応
とくに東大地理では、近年「地理的視点で現代社会の課題をどう説明できるか?」を問う論述が増えており、その“背景知識”のインプットに非常に有効です。
●使い方
- 時事問題やニュースで気になった用語をピンポイントで調べて理解する辞書的使い方がおすすめ。
- 過去問や模試で「なぜそのテーマが重要なのか?」と感じたら、対応する用語を調べて背景と因果関係を整理。
- 「今日は2〜3語だけ読む」と決めて、毎日少しずつ読み進めるだけでも知識のストックが増える。
- 特に**「論述で使えるワードのストックが少ない」**と感じる人には、表現の幅を広げる補助教材としても◎。
論述で差がつくのは、“いかに地理と社会のつながりを深く捉えているか”です。
その力を、楽しく・手軽に鍛えられる一冊です!
3.東大地理の勉強法
0:義務教育レベルの復習
●目的
東大地理は「地理探究」の知識が前提になりますが、その前に必要なのが中学地理=義務教育レベルの基礎の確認です。
なぜなら、東大の問題は「高校地理の応用」ではあっても、
- 都道府県や国名・地形などの位置関係
- 気候・産業・交通・人口分布などの基本事項
といった“中学で学ぶレベルの知識”が土台になっているからです。
また、「高校では地理を選択しなかった」「中学時代の地理の記憶が曖昧」という受験生も少なくありません。
そんな方こそ、地理の「そもそも」を復習しておくことが、後の学習効率と論述力の基盤につながります。
●使用教材
- 『改訂版 中学入試にでる順 社会 地理』
→ 出題頻度順に中学地理を効率よく復習。日本地誌の再整理に最適 - 『高校入試 実力メキメキ合格ノート 中学地理』
→ 講義形式+図表で、ゼロからでもわかりやすい導入教材。整理ノート付きでアウトプットも可能
●勉強の進め方
- 最初の1〜2週間で集中して中学地理を総ざらい
- 目標は「用語を全部覚える」ではなく、「地理の全体像・テーマのつながり」を取り戻すこと。
- 1日1〜2単元のペースでサクサク読み進める
- 地図・統計・グラフは“どう読み取るか”を意識。
- 巻末のまとめ・整理ノートで知識の確認&再定着
- 都道府県や世界地理の地図、気候・産業の分類などは何度も目を通す。
- 気になるテーマ・語句は付箋でマーキングし、次の学習で深掘りできるように
1:基礎知識のインプット&アウトプット
●目的
この段階の目的は、東大地理の論述に必要な「基礎知識の理解と定着」です。
- 単なる丸暗記ではなく、「なぜそうなるのか?」という因果関係を意識した知識のインプット
- 暗記しただけで満足せず、アウトプット(問題演習)で再確認し、使える知識へと昇華
このサイクルを回すことで、地理の基本構造が頭の中に地層のように積み重なっていきます。
●使用教材
- 『村瀬のゼロからわかる地理B 系統地理編・地誌編』
→ 因果関係を理解しながら、地理の“しくみ”を学べるインプット教材 - 『地理一問一答【完全版】3rd edition(東進ブックス)』
→ 圧倒的な問題数と頻出度表示で、効率よくアウトプット可能 - 補助教材:用語集(例:『瀬川&伊藤の地理用語集』)
→ 曖昧な語句や論述で使いたい言い回しを補強
●勉強の進め方
- まずはインプット重視で『村瀬のゼロからわかる地理B』を読む
- 系統地理編と地誌編に分かれているので、まずは系統から始めて「地理的思考法」を習得。
- 図やコラムを飛ばさずにじっくり読むのがポイント。「なぜ?」を説明できるよう意識。
- インプット後すぐに『地理一問一答』でアウトプット演習
- 読んだ範囲の★★★語句を中心にチェックテスト感覚で解く。
- 赤シートを活用して“暗記→確認→再インプット”のループを短時間で回す。
- 苦手分野やうろ覚え語句は、用語集で意味・使い方を確認
- 特に論述で使いたいキーワードは「正確な定義」と「背景知識」を押さえておく。
- 1〜2ヶ月で、村瀬→一問一答を各1周が目安
- その後も過去問演習と並行しながら「反復」と「穴埋め」を継続。
2:論述対策のための知識の整理
●目的
この段階の目的は、覚えた知識を“論述で使える形”に再構築することです。
- どんな統計や地理現象が、どう説明に活かせるのか?
- 知識同士をどう因果的に、論理的につなげるか?
- どの言葉・グラフ・視点を使えば説得力ある答案になるか?
単なる暗記では高得点は取れません。
「知識の意味」と「使い方」を整理し、答案の“構成材料”として引き出せる状態に整えるのがこのフェーズです。
●使用教材
- 『新詳 資料地理の研究』
→ 統計+背景解説で論述のための“根拠”が学べる資料集。図表も豊富で理解が深まる - 『新詳地理資料 COMPLETE』&『図説地理資料 世界の諸地域NOW』
→ 系統・地誌を分担して徹底フォロー。最新の時事問題・SDGsなどの論点にも対応 - 補助教材:用語集(例:『瀬川&伊藤の地理用語集』)
→ 曖昧な語句の意味確認、論述用語の定着、答案表現の引き出しを増やす
●勉強の進め方
- 過去問を数年分解いた後、「書きづらかったテーマ」を振り返る
- 過去問演習と並行してそのテーマに関連する統計・図表・背景知識を資料集で深掘り
- 『新詳 資料地理の研究』をテーマ別に通読&メモ化
- 図・統計を眺めるだけでなく、「この図はどう読み取ればいい?」と問いながら整理
- 特に論述頻出テーマ(都市・気候・農業・人口など)を重点的に
- または、『新詳地理資料 COMPLETE』&『図説NOW』の使用も有効
- 系統地理は『COMPLETE』、地誌は『NOW』で学ぶ。
- 用語集を使いながら「論述で使える語彙・表現」をピックアップ
文章で使うための言い回し、つなぎ語(〜を背景に、〜の影響で、など)もストックしていきましょう。
3:論述問題演習=東大地理過去問演習
●目的
ここでの目的は、いよいよ「実際に書く力=論述力」を完成させることです。
与えられた資料・統計・テーマを読み取り、自分の知識と地理的思考力をもとに、30〜90字という制限字数の中で「的確に、簡潔に、論理的に」書く力を身につけることが、東大地理で合格点を取るための最終ステップです。
●使用教材
- 『東大入試詳解25年 地理〈第3版〉(青本)』
⇒東大過去問25年分+解答・解説収録。記述問題の採点基準や論点の傾向分析にも優れる
●補助教材(状況に応じて使い分け)
- 『村瀬のゼロからわかる地理B』:知識の再確認・因果関係の整理
- 『新詳 資料地理の研究』or『新詳地理資料 COMPLETE+図説NOW』:統計・図表・論述の根拠補強
- 『瀬川&伊藤の地理用語集』:適切な表現・語彙の補強
- その他:用語集類を併用し、知識の精度を高める
●勉強の進め方
- まずは「東大入試詳解25年(青本)」を使い、過去問を1問ずつ丁寧に解く
- 解いた後は、模範解答・解説を読み、論点・語句・構成を比較して自己添削
- 「何が足りなかったか」「どの語句・表現が効果的だったか」をメモしておく
- 繰り返し演習し、「型」を体に覚え込ませる
- 必要に応じて、補助教材で知識の補強を同時に行う
答案が浅くなった原因を探り、資料集や用語集を活用して“論述の土台”を再構築
●演習のコツ
- 「なぜ?どうして?」を常に問う姿勢で答案構成
- 記述内容に“背景・因果・具体例”を必ず盛り込む
- 同じ設問を数か月後に“書き直してみる”ことで成長実感&表現力の確認
この段階は「勉強してきたすべてを答案に落とし込む」総仕上げの時間です。
論述問題を繰り返し演習することで知識が“使える知識”に変わり、地理の得点が安定し始めます。
4:時事問題の対策
●目的
東大地理では近年、時事性の高いテーマを地理的に考察させる問題が頻出しています。
たとえば過去には、
- ファストファッション
- テレワーク
- 海洋プラスチック問題
など、「ニュースで見かけるテーマ」が出題されてきました。
「時事×地理」の視点がなければ論述が書けません。
このステップの目的は、“時事ワードを地理の言葉で説明できる力”をつけることです。
●使用教材
- 『マンガでわかる!中学入試に役立つ教養 地理153』
→ 環境・産業・人口・交通など、地理的テーマに特化した時事用語集 - 『マンガでわかる!中学入試に役立つ教養 政治・国際164』
→ 政治・経済・国際問題など、“地理的視点”が問われる社会問題を幅広くカバー
これらは中学入試向けと侮るなかれ。東大論述にそのまま使えるトピックが満載です。
むしろ、マンガと図解で「直感的に理解できる」からこそ、難しい話題でも地理的に考える視点が身につくというメリットがあります。
●勉強の進め方
- 基本は、「少しずつ、継続的に」読む
- いきなり全部やる必要なし。1日2〜3語ペースでOK。
- 週3〜4日、スキマ時間に読む習慣をつけると◎。
- マンガページで直感的に理解 → 特集ページで背景を確認
- 重要なのは「なぜそれが問題なのか?」「地理とどう関係しているのか?」を理解すること。
- 過去問で関連テーマが出たら、その都度確認して補強
- 例:「観光問題」が出たら「オーバーツーリズム」などを即チェック。
- 知識を“答案に活かせる形”でメモしてストック
- A6ノートなどに、自分なりの要約や例文をメモしておくと、論述の引き出しが増える。
この時事対策を続けることで、「あ、このテーマ、あのマンガで読んだやつだ!」という“地理的に考える感覚”が自然と養われていきます。
4.東大地理の受験勉強スケジュール例
① 理想パターン
●スケジュールの流れ
- 高2の2月〜高3の5月
→ 『村瀬のゼロからわかる地理B』+『地理一問一答』で、基礎知識のインプット&アウトプット - 高3の6月・7月
→ 『新詳 資料地理の研究』や資料集を使って、論述に必要な知識・構成力を整理 - 高3の8月以降
→ 青本で過去問演習本格スタート。論述問題を実践的に書く訓練へ - 必要性を感じたタイミングで
→ 『マンガでわかる!』シリーズなどを活用し、時事問題対策を随時取り入れる
●特徴
このパターンは、地理を得点源にしたい人・計画的に地理を完成させたい人向けの最も理想的なプランです。
- ステップごとに時間的余裕があり、「理解→整理→実践」のプロセスがスムーズに流れる
- 時事問題にもフレキシブルに対応可能で、東大地理の出題傾向にきめ細かく対応できる
- 高3の夏以降は、他科目の比重が増しても地理に焦らず取り組める体制が整う
●良い点
- 焦らずじっくり論述力を鍛えられる
- 時事・地誌・統計など、あらゆる地理の要素を段階的にマスターできる
- インプットとアウトプットを並行することで、知識の定着率が非常に高くなる
- 復習や応用に時間を割ける“余白”があるので、答案の質を上げやすい
●注意点
- 開始が遅れると全体が後ろ倒しになるリスクあり
→ 高2の終わり〜高3春に“地理の土台”を作れなかった場合、夏以降の演習時間が圧迫される - 一度やったことを“忘れない”ための復習計画もセットで立てること
② 夏休み中追い込むパターン
●スケジュールの流れ
- 高3の6月・7月
→ 『村瀬のゼロからわかる地理B』と『地理一問一答』で、基礎知識を集中インプット&アウトプット - 高3の8月(夏休み)
→ 『資料地理の研究』や『地理資料集』を使い、論述向けの知識整理を一気に進める - 高3の9月以降
→ 『東大入試詳解25年(青本)』で、論述問題の本格的な演習スタート - 必要性を感じたタイミングで
→ 『マンガでわかる!』シリーズで、時事問題対策を柔軟に追加
●特徴
このパターンは、高3の6〜7月から本格的に地理対策を開始し、夏休みに地理を一気に仕上げる“短期集中型”のスケジュールです。
- 地理に本格着手する時期が遅めでも、夏休みを最大限活用すれば巻き返しが可能
- 短期間で地理の基礎→論述まで進むため、集中力と継続力がカギ
●良い点
- 夏休みにまとまった時間を確保できる人には最適→1日2〜3時間×1ヶ月で、実質60時間以上の地理学習が可能
- 勢いで一気に仕上げられるので、学習内容がつながりやすい→短期間で学んだ知識は「連続性」があるため、論述への応用もスムーズ
- 他科目の進度を見て調整しやすい柔軟さもある
●注意点
- 準備期間が短いため、基礎が不十分なまま応用に進んでしまうリスクあり→村瀬や一問一答を「2周以上」するつもりで使い込む必要あり
- 夏休み中に“サボったら終わり”の危険性→明確な1日ごとの目標設定と進捗管理が不可欠
- 過去問演習に割ける時間が理想より少なめになる可能性も→9月以降、週1〜2問のペースで“継続的に過去問を解く”習慣をつけること
③ 他科目との兼ね合いで地理にあまり時間を割けないパターン
●スケジュールの流れ
- 高3の4月〜7月
→ 『村瀬のゼロからわかる地理B』+『地理一問一答』で、基礎知識を最低限インプット&アウトプット - 高3の8月以降
→ 過去問を解きながら、『資料地理の研究』や資料集で論述対策のための基礎知識を並行整理 - 共通テスト後
→ 『マンガでわかる!』シリーズ等で時事問題の対策を集中実施
●特徴
このパターンは、英数国や理系科目との兼ね合いで地理にまとまった学習時間を割けない受験生向けの現実的戦略です。
- 地理に“1日1時間も取れない”という前提の中で、最小限の労力で最大の成果を狙う
- 過去問を“教材化”し、インプット・アウトプット・論述訓練を一体化して進めるのがポイント
●良い点
- 「とにかく効率優先」で動けるため、他科目とのバランスが取りやすい
- 過去問を軸に据えることで、実戦力を短期間で引き上げやすい
- 基礎→実践→時事と、段階的に知識を伸ばす流れは維持されている
- 地理が得意・好きな人なら、少ない勉強時間でも高得点が狙える
●注意点
- 基礎の理解が不十分なまま論述演習に入ってしまう可能性→村瀬・一問一答は“短期間でも2周”が前提
- 過去問演習の「質」がすべて→書いて終わりではなく、模範解答の分析+知識の補強+表現力の強化までやり切ること
- 時事問題への対応が後手に回る可能性→共通テスト直後から「1日1語」のペースで『マンガでわかる!』を読み始めるなど、ルーティン化が重要
✅ スケジュール別のおすすめ受験生タイプまとめ
| パターン | こんな受験生におすすめ |
| ① 理想型(高2終〜高3春から) | ・地理を得点源にしたい人 ・早めに受験勉強を始めている人 |
| ② 夏休み追い込み型 | ・部活引退後に本腰を入れる人 ・6月〜7月から本格始動したい人・短期集中が得意な人 |
| ③ 他科目重視型(地理省エネ) | ・英数国に時間を取られる人 ・地理を“効率よく”仕上げたい人・地理が得意 or 好きな人 |
どのパターンでも「受験本番で地理を武器にする」ことは可能です。
大切なのは、自分の状況や特性にあったルートを見極めて「このやり方で行く」と腹を決めることです。
5.東大地理の勉強で陥りがちな罠&対策
① 地理=暗記科目だと思い込む
地理というと、「用語や統計をひたすら覚えるだけの暗記科目」と思ってしまいがちです。
しかし、東大地理では「その知識をどう使うか」が問われます。「人口が多い」→「なぜ多いのか」「他地域とどう違うのか」といった因果関係や比較視点がなければ、論述では点が伸びません。
対策としては、『村瀬のゼロからわかる地理B』や資料集を活用し、地理的な“なぜ”を常に意識して学ぶ姿勢を持ちましょう。
② インプットだけで満足し、アウトプットを後回しにする
地理の用語集や参考書を読んで「わかった気になる」のは危険です。
読んだだけの知識はすぐに忘れますし、実際の論述で使えるレベルにはなっていません。
この罠を避けるには、『地理一問一答(東進)』などを使って、毎日の中で「必ずアウトプットをする時間」を設けることが大切です。
演習と確認を繰り返す中で、知識が「使えるもの」に変わっていきます。
③ 論述対策を後回しにしてしまう
「まずは知識を完璧にしてから論述を始めよう」と思っていると、いつまでも過去問に手を出せず、入試が近づいてから焦るパターンに陥ります。
東大地理の論述は慣れと構成力がモノを言うので、ある程度知識が入った段階で、少しずつ演習を始めることが重要です。
最初は模範解答を真似る形でも構いません。
答案構成のパターンに慣れることが、得点力アップへの近道です。
④ 時事問題への意識が低い
東大地理では「地理×現代社会」を考えさせる問題が増えていますが、「地理に時事は関係ない」と思って後回しにしてしまう受験生も多いです。
こうした傾向に対抗するには、『マンガでわかる!地理153』や『政治・国際164』などを日常的に読み進め、時事ワードと地理的背景のつながりを“ゆるく”学び続けることが効果的です。スキマ時間でサッと読める形式なので、勉強の負担にもなりません。
⑤ 書いた答案を「自己流」で終わらせてしまう
論述問題を書いても、「なんとなくよく書けた気がする」で終わらせてしまうと改善点が見えず、成長しにくくなります。
答案を完成させたら必ず模範解答や解説と比較し、「どこが足りなかったのか」「どの表現が効果的だったのか」を確認しましょう。
自分の答案を「採点者の目線」で見る癖をつけることで、論述の質はぐっと上がります。
⑥ 学習スケジュールの偏り
「基礎ばかりやっていて論述が手つかず」「いきなり演習に突っ込みすぎて知識が浅い」といった偏った学習パターンも危険です。
東大地理は、基礎→整理→演習→時事という4段階をバランスよく繰り返すことが成功のカギです。
1ヶ月ごとに「今、自分はどの段階にいるか?」を振り返る習慣をつけましょう。
6.東大地理の勉強法まとめ
東京大学の地理は単なる知識量や暗記力では通用しない、“思考力勝負”の記述型試験です。
論述問題の出題、時事テーマへの対応、日本地誌の重視…どれをとっても、知識を「使えるかどうか」が試されます。
しかし、だからこそ正しいステップを踏めば独学でも、地理が苦手な人でも、着実に得点源へと育てていくことが可能な科目でもあります。
✅ 東大地理攻略の4ステップ
- 中学地理レベルの復習で“地理の型”を思い出す
→ 『でる順地理』『実力メキメキ合格ノート』 - 基礎知識の理解と反復で“地理の骨格”を作る
→ 『村瀬のゼロからわかる地理B』『地理一問一答』 - 資料集と論述練習で“地理的な思考力”を鍛える
→ 『資料地理の研究』『青本』『地理資料集』『用語集』 - 時事テーマで“実戦力”を完成させる
→ 『マンガでわかる!地理153』『政治・国際164』
✅ あなたの状況に応じた戦略を選ぼう
- 早めに始めて地理を得点源にしたいなら「理想スケジュール型」
- 他科目が忙しい人でも「夏休み追い込み型」や「省エネ型」で対応可能
- いずれも「基礎→整理→演習→時事」の流れを意識すればOK
✅ 最後にひとこと
東大地理は、“やれば確実に伸びる科目”です。
才能やセンスではなく、順番と戦略と継続の3つが成功のカギ。
地理の勉強を通じて世界の見え方が変わり、社会問題に対する理解も深まります。
それはきっと、東大合格だけでなく大学で学び続けるための知的体力にもなるはずです。
この記事を読んだあなたが、自信を持って東大地理に立ち向かえるよう応援しています!