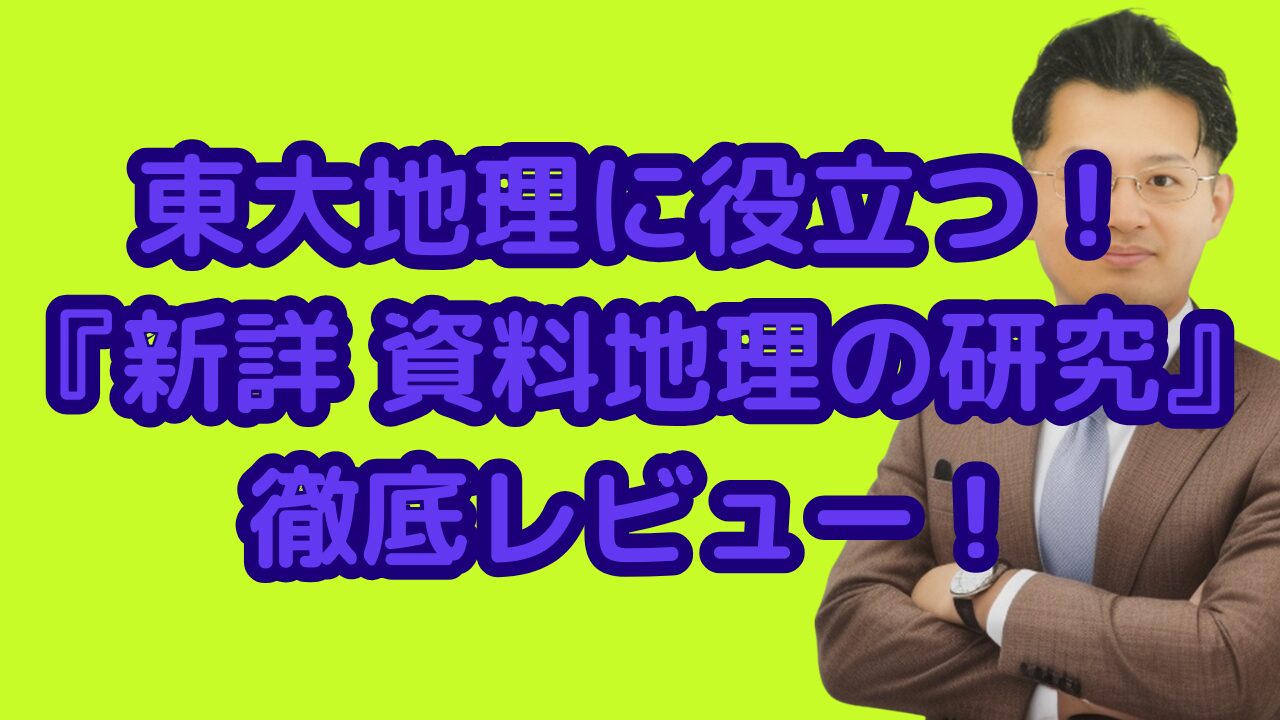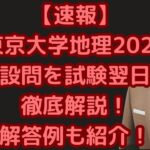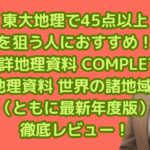東大地理の論述問題では、単なる知識の暗記ではなく、データを活用しながら論理的に説明する力が求められます。しかし、「何を書けば点が取れるのか分からない」「解説は読んだけれど背景まで理解できていない」と悩む受験生も多いのではないでしょうか?
そんな東大地理対策において、「論述の辞書」として活用できるのが、帝国書院の『新詳 資料地理の研究』です。
本書は、統計資料や図表が豊富に掲載されており、単なるデータの羅列ではなく、地理的な現象の背景まで詳しく解説されているのが特徴。
「なぜその現象が起こるのか?」を論理的に理解し、答案に活かすことができる1冊です。
本記事では、東大地理受験生にとって『新詳 資料地理の研究』がどのように役立つのか、使用タイミング・目的・メリット・注意点・効果的な活用法まで徹底的にレビューしていきます!
1:『新詳 資料地理の研究』とは
基本情報
| 項目 | 内容 |
| 執筆者 | 新井祥穂、江崎雄治、小槻文洋、木村圭司、近藤章夫、佐々木緑、堤純、仁平尊明、半澤誠司、堀和明、武者忠彦、山内昌和 |
| 出版社 | 帝国書院 |
| 発売日 | 2021年3月15日 |
| 定価 | 1,026円(税込) |
| ページ数 | 345ページ |
📌 基本構成
本書は、文章・統計資料・図表を用いて地理のさまざまな現象やその背景を詳しく解説する構成になっています。
ただ単にデータを並べるのではなく、なぜそのような現象が生じるのかを論理的に説明している点が特徴です。
地理的思考力を鍛えるのに最適です。
📚 目次構成
本書は 5つの主要パート に分かれており、地理の基礎から応用まで体系的に学べるようになっています。
1️⃣ 地球の自然環境
- 地形
- 気候 ほか
2️⃣ 資源と産業
- 世界の農業形態
- おもな農畜産物の生産と流通 ほか
3️⃣ 生活・文化とグローバル化
- 村落・都市
- 消費・余暇活動 ほか
4️⃣ 世界の諸地域
5️⃣ 地理情報と地図
🔹 巻末資料:補助データや統計のまとめが掲載されており、論述対策にも役立つ。
2:『新詳 資料地理の研究』の使用タイミングと使用目的
📌 使用タイミング
『新詳 資料地理の研究』は、地理の基礎を固めた後に活用するのがベストです。
✅入門教材(インプット)+一問一答・ドリル(アウトプット)を終えた段階
- 例えば、『村瀬のゼロからわかる地理B』などで系統地理・地誌を学び、一問一答やドリルで基本知識を整理した後に使うことを推奨。
- いきなり本書から始めるのは非推奨!(情報量が多く、初学者には情報の取捨選択ができずハードルが高い)
✅ 東大地理過去問演習や論述演習時の「辞書」として
- 論述の際に必要なデータや現象の背景を素早く調べるために活用。
- 過去問の解説(特に青本)が細かすぎると感じる場合、本書と照らし合わせることで重要なポイントを取捨選択できる。
🎯 使用目的
📌 論述演習前
東大地理論述に必要な知識の整理と地理的思考力の向上
- 「なんとなく知っている」状態から、「論理的に説明できる」状態へ
- 統計データ・図表を活用しながら論述を組み立てる準備
📌 論述演習中
取り組んでいる問題の解答作成に必要な知識を整理・確認
- 「このデータを使ったら説得力が増しそう!」
- 「この現象の背景は何だったっけ?」
- → 本書を活用して、答案の精度を上げる!
3:『新詳 資料地理の研究』の特徴とメリット
『新詳 資料地理の研究』は、東大地理の論述対策において「辞書的に使える最強の資料集」です。
統計データ・図表・解説が充実しており、論述問題を解く際の大きな助けとなります。
📌 主な特徴とメリット
✅ 入試頻出の統計資料や図表が豊富!
- 東大地理ではデータを活用する必要のある論述が頻出
- 本書には 最新の統計や図表が多く掲載 されており、データを論述の根拠として活用できる
✅ 現象の背景まで詳しく解説!
- ただ統計を載せるだけでなく、「なぜこの現象が起きるのか?」を論理的に説明
- 因果関係の理解が深まり、論述答案の説得力がアップ!
✅ 情報量が多い → 論述演習時に調べるのに便利!
- 過去問演習で疑問に感じた点をすぐに調べて解決できる
- 例えば「温室効果」や「モンスーン気候」など、気候や産業の背景知識を補強するのに最適
✅ 東大地理の過去問演習の際の調べものを1冊に集約できる!
- 青本(25ヵ年)の解説が細かすぎるとき、本書と照らし合わせるとポイントが整理しやすい!
- 辞書的に使うことで、過去問演習の効率アップ!
✅ 東大地理の出題事項のカバー率が高い!
- 東大地理で頻出のテーマがしっかり解説されている
- 実際の過去問との対応例を見ても、十分なカバー率があることが分かる!
📚 東大地理2025の問題との対応例(実際の活用シーン)
📌 「北半球高緯度地域の気温上昇が他地域より大きい理由」
➡ 『新詳 資料地理の研究』で温室効果のメカニズムが文章と図で解説されている!
➡ これを理解していると、地球温暖化に関する論述がスムーズに書ける
📌 「海面上昇の要因」
➡ 『新詳 資料地理の研究』に海面上昇の要因が明記されている!
➡ そのまま答案に使える知識として活用可能
📌 「日本において、中国からの衣類輸入割合が低下している理由」
➡ 『新詳 資料地理の研究』では、労働力指向型の工業の例として繊維工業が挙げられている!
➡ 生産コストや労働賃金の変化を考慮した、東大の求める本質を突いた論述が可能に
4:『新詳 資料地理の研究』の効果的な使い方
『新詳 資料地理の研究』は、単なる読み物ではなく、東大地理の論述対策を強化するためのツールとして活用するのがベストです。
以下のように使うことで、地理の知識を効率的に整理・活用できます。
① 基礎知識のインプット・アウトプットを終えた後に通読
🔹 方法
- 一通り読む(完璧に暗記する必要はなし!)
- 主要な統計・図表・概念のページに付箋を貼る
- どこに何が書いてあるのか大まかに把握する
- 過去問演習前に、関連する章をざっと確認
- 例えば「地形」に関する問題を解く前に、「地球の自然環境」の章をチェック
- 東大地理の過去問演習をスムーズに進めるために、必要な情報をすぐに見つけられるようにする
- 調べる時間を短縮し、答案作成のスピードを上げる!
② 論述演習時の「辞書」として活用
🔹 方法
- 過去問の設問を確認 → どの知識が必要か考える
- 本書の対応するページを調べ、解答に必要な情報を抽出
- 過去問集の解説と照らし合わせ、「覚えるべきこと」と「細かすぎる部分」を取捨選択
5:『新詳 資料地理の研究』の使用上の注意点
『新詳 資料地理の研究』は非常に優れた資料集ですが、使い方を間違えると効果が半減してしまいます。
以下の注意点を意識しながら活用しましょう。
📌 ① 初学者向けの教材ではない
✅ いきなりこの本を読み始めるのはNG!
- 『新詳 資料地理の研究』は、詳細な統計や地理的背景の解説が豊富なため、基礎知識がないと理解しづらい。
- まずは入門書(例:『村瀬のゼロからわかる地理B(系統地理編・地誌編)』)を通読し、基本概念をインプットする。
- 一問一答やドリル形式の問題集(例:東進の『地理B 一問一答』)でアウトプットし、知識を定着させる。
📌 ② 通読に時間をかけすぎない
✅ インプット過多にならないよう注意!
- 「完全に覚えてから論述演習に進もう」と考えるのは間違い!
- 完全に覚えていなくても構わないので、すぐに論述の問題演習に入る。
- 論述の中で「知識が足りない」と感じたときに本書を辞書的に活用するのがベスト!
📌 ③ 2021年発売のため、最新の時事テーマには未対応
✅ 2026年度入試以降では最新時事を補う必要あり!
- ロシアのウクライナ侵攻(2022年~)など、最新の国際情勢についての記述はなし。
- 近年の気候変動やエネルギー問題などの新たなデータが反映されていない可能性がある。
- →最新時事は新聞・ニュース・資料集(『最新地理資料(帝国書院)』など)で補強!
📌 ④ これ1冊だけで東大地理対策が完結するわけではない
✅ 東大地理は「出題の切り口」が広い!
- 『新詳 資料地理の研究』は非常に情報量が多いが、東大の論述問題ではこの本に載っていないテーマが出題されることもある。
- 最新の時事問題や、独自の視点を求められる問題には対応しきれない場合がある。
→「この1冊だけで十分」と過信せず、過去問や他の参考書と併用することが重要!
6:『新詳 資料地理の研究』を実際に使った受験生の声
実際に『新詳 資料地理の研究』を活用した受験生のリアルな感想を紹介します!
良かった点 と いまいちだった点 の両方をまとめました。
📢 良かった点
🗣 「論述の根拠が増えて、答案が書きやすくなった!」(東大文三志望)
➡ 東大の地理論述って、ただ現象を知ってるだけじゃダメで、「なぜ?」を説明しないと点がもらえない。でも、この本には 温暖化のメカニズムとか、産業の立地条件の理由とかがちゃんと図と一緒に説明されてるから、論述に使える知識が増えた!
🗣 「データが豊富で、統計を使った論述がしやすい!」(東大文一志望)
➡ 東大の地理は 統計を使って説明すると点がもらいやすい って言われるけど、この本は統計が多いから助かった! 例えば、農業生産やエネルギー消費のデータが載ってるから、論述の時に「この国の輸出量は〜」みたいに具体的な数字を入れて答案を書けた。
🗣 「東大地理の辞書として最強!」(東大文二志望)
➡ いちいちネットで調べたりするのが面倒だったけど、この本があれば 論述で使えそうな知識をすぐに確認できる から、過去問演習の効率が上がった! 青本(25ヵ年)の解説って長すぎて読むのが大変だけど、この本はポイントが整理されてるから、重要な部分だけチェックしやすい!
⚠ いまいちだった点
🗣 「最初から読むのはキツすぎる…」(東大文二志望)
➡ 地理が得意じゃないのに この本を最初から読もうとしたら、情報量が多すぎて挫折した…。 「これは辞書的に使う本だな」って途中で気づいたけど、最初に入門書(『村瀬のゼロからわかる地理B』とか)を読んでおけばよかったと思った。
🗣 「通読しようとすると時間がかかりすぎる」(東大文三志望)
➡ 「全部読んで理解しよう!」と思ったら、めっちゃ時間がかかった…。結局、論述演習の時に必要な部分だけ調べる使い方が一番いいってことに気づいた。これをメインの勉強にすると、過去問演習が遅れるから注意!
🗣 「2021年版だから、最新の時事問題が載ってない」(東大文一志望)
➡ ロシアのウクライナ侵攻とか、最近のエネルギー問題についての記述がない から、時事問題系の論述ではこの本だけだと足りないかも。
7:『新詳 資料地理の研究』の記事のまとめ
📌 使用タイミング
✅ 基礎知識(入門書+一問一答)を学んだ後に活用
✅ 東大地理の過去問・論述演習の際に辞書として使う
✅ 最新時事問題は他の資料で補う必要がある
📌 メリット
✅ 東大地理で頻出の統計資料・図表が豊富!
✅ 現象の背景まで深掘りした解説で論述力アップ!
✅ 論述の根拠となるデータをすぐに確認できる!
✅ 青本(25ヵ年)の解説が細かすぎるとき、情報整理に便利!
📌 効果的な使い方
✅ 最初に軽く通読し、どこに何があるか把握!
✅ 論述演習の際に「辞書」として活用!
✅ 過去問の解説と照らし合わせ、必要な知識を取捨選択!
8:さいごに
『新詳 資料地理の研究』は、東大地理の論述対策において 「辞書的に活用できる最強の資料集」 です。
統計や図表が豊富で、地理的な現象の背景まで詳しく解説されているため論述の説得力を高めるのに最適です。
しかし、この1冊だけで地理対策が完結するわけではありません。
- まずは入門書や一問一答で基礎を固める
- 論述演習を通して、必要な知識を辞書的に補う
- 最新の時事問題は他の資料で補強する
このように、正しい使い方を意識することで、東大地理の得点力を大幅に向上させることができます!
「過去問を解いたけど、知識が足りない…」「論述の根拠を強化したい!」と感じたときこそ、『新詳 資料地理の研究』を活用するベストタイミングです。
地理の学習をより効率的に、そして論理的に進めるために、この1冊をうまく使いこなしていきましょう。